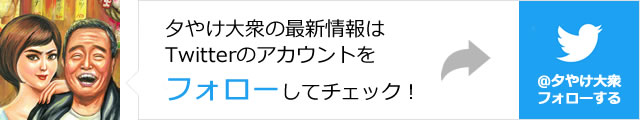Catch Up
キャッチアップ
Catch Up
キャッチアップ

この官能小説は、現在50代から60代の方々の若かりし時代を舞台背景にしています。貧しかったけれど希望に満ち溢れていたあの頃、そこには切なくも妖しい男と女の物語が今よりも数多く存在しました。人と人とが巡り合う一瞬の奇跡、そこから紡がれる摩訶不思議な性の世界をお楽しみください。 編集長
【同棲相手との40年ぶりの再会】
60歳で定年を迎え、嘱託で会社に残る選択もあったが、そのまま退社。その後はシルバーセンターの派遣で、小田は駅前の駐輪場で働いていた。
おもな仕事は自転車の整理と管理。雑然と並んだ自転車を可能な限り詰め込み、奥まった場所にあるものは利用者に代って取り出す。多忙になるのは朝と夕方で、それ以外の時間は暇を持てあますことが多い。
その閑散とした時間帯に、彼女は訪れた。
「すいません。どこに停めれば」
女性は事務所に声をかける。昼食を終えたばかりの小田は、駐輪場に出て空きスペースを探す。
「奥のほうしか空いてませんね。カギをかけていただければ、わたしが移動させますよ」
小田は、そういって女性の顔を見た。
毎日のように利用する人の顔ならおぼえている。しかし、女性は初めて見る顔立ちをしていた。だが、記憶の奥に面影が残っているようにも思う。それは女性のほうも同じだったようだ。
小田の顔から胸もとにある名札に、彼女は視線を移した。そこには小田のフルネームが記されている。
「裕也?」
「え?」
「裕也でしょ。わたし、沙織」
小田の記憶がよみがえった。
長かった髪は短く切りそろえられている。目尻にうっすらとしわが刻み込まれている。ほほにかすかなシミが浮かんでいる。
そんな年齢を経た変化は見られるものの、彼女はたしかに沙織であった。
「久しぶり。おぼえてる?」
「ああ、もちろん」
笑みを浮かべる沙織に、小田も笑顔で答える。
「こんな仕事してるんだ」
「こんな仕事って、立派な職業だよ」
「あ、ごめんなさい。そんなつもりじゃ……」
「相変わらずだなぁ。すぐに謝るクセ」
小田は破顔する。それに合わせて沙織の笑顔も満面にひろがった。
「あ、ごめんなさい、急がなきゃ」
「うん、自転車は移動させておきます」
「ありがとう。きょうは何時までお仕事?」
「4時まで」
「残念、帰りは会えないわね。毎日、ここにいるの?」
「週に4日、月曜から木曜」
「わかった」
沙織は、そう言い残して立ち去る。小田は沙織のワンピースの裾がひるがえるようすをながめながら、彼女の後ろ姿を見送った。
数日後、ふたたび沙織は駐輪場を訪ねてきた。ただ、自転車はない。沙織の目的は小田だ。
「こんにちは。きょうは何時まで?」
「きょうも4時まで」
「じゃあ、そこの喫茶店で待ってる」
沙織は、駐輪場から100メートルほど離れた店を示す。
「なにか用なの?」
「ううん、用がなくちゃ会っちゃいけないの?」
「いや、そんなことはないけど」
沙織はブレスレット状の腕時計を見た。
「あと40分くらいね。待ってるから」
深い秋が金木犀の香りを運んでいる。午後の日差しが、やわらかくコンクリートの床に差し込んでくる。そろそろ学校帰りの学生で込み合う時刻だ。
沙織は喫茶店に向かう。小田は事務所の前にかけられた丸い時計を見る。規則正しい秒針動きを、まどろっこしく感じながら。
勤務を終えて沙織の指定した喫茶店に入る。沙織は紅茶のカップを前にし、文庫本を開いていた。
「お待たせ」
小田が声をかけると、沙織は笑顔で顔をあげる。むかしのままだ、と小田は思った。
「ホント、びっくりしちゃった。あんなところ……、あ、ごめんなさい。そんなつもりじゃ」
「いいよ、きみにとってはあんなところだ。でもボクにとっては大切な職場だ」
「そんな意味じゃないの。決して……」
「ごめん、ごめん。責めてるわけじゃない」
小田の前に温かいコーヒーが運ばれてくる。湯気に含まれる濃厚な香りが、小田の神経をおだやかにする。
「その後、どうしてたの?」
会話の口火を切ったのは沙織のほうだった。
「定年まで会社にいて、それから……」
「そんなことじゃない。わたしたちがサヨナラしてから」
沙織は口角をあげつつも、唇を固くする。
「広告代理店で営業をしていた」
「広告業界はあこがれだったもんね」
「うん。けど、本当は」
「小説家になりたかった。というよりも、言葉を使う仕事がしたかった。だからコピーライターになりたかった」
「よく、おぼえてるね」
「あなたのことは……」
沙織は口に出しそうになった言葉をつぐんだ。
「そうだ、いまクルマは?」
「もうハンドルは握っていない。必要ないし、それに……」
「いまのクルマには魅力を感じない。違う?」
沙織は小田の心内を見透かすようにいう。
「きみのいうとおりだ。効率を重視したコンピュータのデザインに、子どもでも運転できる機能。自動運転を否定はしないけどね」
「重たいハンドルとマニュアルのミッション。そしてクラッチ操作。それがドライブの醍醐味」
「詳しいね」
「あなたの受け売りよ」
沙織は上目づかいで小田を見ながら、カップを口に運ぶ。
「ところで、きみは、いまは?」
「一人で暮らしてます。子どもは近くに住んでいて、時々、孫の世話もみているわ」
「だんなさんは?」
「10年前に死んじゃった。ガンで」
「そうなんだ」
小田は、一口コーヒーをすする。心地よい苦みが舌の上にひろがる。
「あなた……、裕也は?」
沙織は小田を名前で呼んだ。
「ボク? ボクは20年前に離婚した。それからは、ずっと一人だ」
「そうなの」
沙織の表情に、かすかな明るさが差す。
「懐かしいわね。裕也と暮らしていたころ。いまでも思い出す」
「そうなの?」
「うん。でも……」
「でも?」
沙織は口をつぐむ。そして紅茶を一口すすると、ごまかすようなほほ笑みを浮かべた。
小田と沙織は、同じ大学の文学部に在籍していた。年齢も同じ。同じ教室で同じ講義を受けているうちに親しくなる。
小田の趣味は読書とドライブ。当時、乗っていたのは父親から譲ってもらったスカイライン。
「よければ、ボクのクルマでドライブしない?」
小田が沙織をデートに誘った最初の言葉だった。
性格はおとなしいタイプの小田だったが、ハンドルを握ると一変する。峠道を好み、曲がりくねった道でタイヤを鳴らしながら走るのを得意とする。そのスピード感に沙織も魅せられてしまった。
ただ、小田のスカイラインにパワーステアリングは装備されていない。しかも、幅の太いタイヤを装着している。駐車場に停めるときはステアリングが重くなり、沙織も助手席からハンドルを切る手助けをすることもしょっちゅうだった。
そんな、ある夏のことだった。
「いやー! やめてー!」
夜の山道を走ったあと、山頂付近の駐車場にクルマを停める。小田と沙織は、眼下にひろがる夜景を楽しんでいた。
そこに1台の派手なクルマがやってきて、男が3人おりてきた。そのうちの二人は、いきなり小田を殴り倒して地面に押さえつけ、残りの一人は自分たちのクルマに沙織を押し込む。
「やめろー! やめてくれー!」
うつぶせになった小田は叫ぶ。叫びながら抵抗を試みるが、二人の力にはかなわない。
「いやー! いやー! やめてー!」
沙織の絶叫がひびく。乗せられたクルマが、ユサユサと上下に揺れる。
やがて沙織の声が途絶えた。それと同時にクルマの揺れも止まり、ズボンのチャックをあげながら男がおりてくる。
「よし、交代だ」
押さえつけていた男の力がゆるむ。そのすきを見て、小田は身体を起こし、沙織を助けようと駆け出す。しかし、すぐにつかまってしまい、3人がかりで殴られ、蹴られ、意識を失ってしまった。
気づいたとき、男たちのクルマも姿もなかった。沙織は乱れた衣装で地面に座り、スカイラインにもたれかかっていた。
「さ、沙織さん……」
小田は立ちあがろうとする。しかし、痛みで身体の自由がきかない。口の中が切れ、血の味がひろがる。
それでも、小田はよろよろと沙織に近寄る。
「ごめん、ごめん、守ってあげられなかった。ごめん」
小田は呆然自失の沙織の頭をかかえ、涙を流して謝る。
「お、小田くん……、わたし、汚されちゃった」
視線を宙に漂わせた沙織はいう。
「汚れてなんかない、汚れちゃいない。ボクが、ボクが……」
小田は沙織の唇に、自分の唇を重ねる。そして、ほほから首筋、胸の辺りに舌を這わせる。男たちから受けた穢れをぬぐい取るように。
「やめて、もういい……」
「よくない。沙織さんが汚れたと思うのなら、ボクが、その汚れをきれいにしてみせる。ボクが一生かけても」
沙織は小田の目を見て涙を見せる。小田は、ふたたび沙織を固く抱きしめた。
それから二人の同棲生活がはじまった。小田は、それこそもとの清浄な姿に戻すよう、毎日毎晩、沙織を抱いた。献身的な小田の行為に、いつしか沙織も溺れてしまう。
朝、一緒に登校し、一緒に下校して買い物を済ませ、食事を終えると狭いアパートの中で互いをたしかめ合った。
「裕也、ステキ、やん、気持ちいい!」
「沙織、きれいだよ、すごくきれいだ。沙織」
飽きるということはなかった。交わることで、生きていると実感できた。
沙織は小田の色に染まることを願った。その思いは、沙織の肉体を女のものへと変化させる。
乳房は大きくなり、腰も締まる。肌艶もよくなり、匂うような色香もにじみ出てくる。
そんな沙織に小田も溺れた。二人は大学にも通わなくなり、食事も満足にとらなくなる。夏が終わり、秋がきて、冬の訪れを知るころになっても、怠惰な生活を改めることはなかった。
「でも、バレちゃったのね、親に」
沙織はいう。
「大学から通知が行くとはね」
小田は照れた笑いを浮かべる。
出席日数が足りず、留年が決定した。その通知が、互いの実家に送付された。驚いた沙織の両親は娘の下宿を訪ねたが、もぬけの殻。同じ理由で小田の両親が息子のアパートを訪ね、二人の同棲が明らかとなる。
「裕也のご両親に悪いことしちゃったな、っていまでも思う。裕也と並んで土下座させてしまったし」
「世間の常識じゃ、男のほうが悪い」
沙織は実家に戻され、大学も辞めた。小田は同じアパートで暮らし続けたが、沙織とは音信不通となる。
「常識かぁ、なんだかなぁ」
沙織は遠くをながめて、紅茶を飲み干した。
「なあ、沙織」
「あ、やっとむかしと同じように呼んでくれた」
カップをソーサーにおいて、沙織はほほ笑む。
「いや……、でさ、沙織」
「なに?」
「いまは幸せなの?」
「うん、裕也は?」
「そうだなぁ、満足はしている。シルバーの仕事をしてるとさ、過去にいろんなことがあった人と知り合える。それこそ、一流企業に勤めていた人とも知り合えるし、逆に苦労を重ねてきた人の話も聞ける」
「それを小説に活かす?」
「いや、もう、小説は……」
「そうなんだ、ちょっとがっかり」
「でもさ」
小田は、少し前屈みになって沙織にたずねた。
「どうしてボクのことを誘ったの?」
「ん? そうねぇ、ちょっとむかしを懐かしんでみたかったのかも」
「それだけ? もし、よければさ……」
言葉を続けようとする小田の唇を、沙織は人差し指で制する。
「ダメよ。わたしは今の生活を失いたくない。孫はかわいいし、安定もしている。それに」
「それに?」
「わたしは、むかしのわたしじゃない。それは裕也も同じでしょ。現実は残酷よ。ゴールしてしまったスゴロクを、もう一度最初からやり直すような人生はおもしろくない」
「思い出は、思い出のまま」
「そう。きょうはありがとう。楽しかった」
「このあと、食事でも」
「そうも考えたけど、もういい。満足しちゃった」
沙織は席から立ち、伝票を手に取る。
「また会いたくなったら、あの駐輪場に行くわね。その時はよろしく」
そう言い残して、沙織は店から出て行った。しかし、その後、沙織が小田のところに姿を見せることはなかった。
季節がうつろい、冬になる。コンクリートに囲まれた駐輪場は、底冷えがする。
「沙織、元気にしているかな」
小田はときおり、沙織のことを思い出す。それは、学生時代の沙織であり、秋に会った沙織でもある。
「お互い、老けちゃったな」
駐輪場の前を、流行りのワンボックスカーが走り抜けた。小田は、その車体をながめながら、短い溜息をはいた。
- 【長月猛夫プロフィール】
- 1988年官能小説誌への投稿でデビュー。1995年第1回ロリータ小説大賞(綜合図書主催)佳作。主な著作『ひとみ煌きの快感~美少女夢奇譚』(蒼竜社)/『病みたる性本能』(グリーンドア文庫)/『19歳に戻れない』(扶桑社・電子版)ほか。
この記事の画像
関連キーワード
 Linkage
関連記事
Linkage
関連記事
-

【昭和官能エレジー】第37回「捨てられた女・捨てられた男」…
-

【昭和官能エレジー】第36回「人生をあきらめた細い身体の女…
-

【昭和官能エレジー】第35回「東京から流れてきた女」長月猛夫
-

【昭和官能エレジー】第34回「追い出された女との束の間の同…
-

【昭和官能エレジー】第33回「留年大学生を男にした下宿屋の…
-

昭和官能エレジー第32回「夏休みの幻 廃屋の女」長月猛夫
-

昭和官能エレジー第31回「年上少女の誘惑」長月猛夫
-

昭和官能エレジー第30回「女になれずに逝った少女」長月猛夫
-

昭和官能エレジー第29回「惑乱された父親の愛人」長月猛夫
-

昭和官能エレジー第28回「教え子の母の誘惑」長月猛夫
-

あの週刊大衆が完全バックアップした全国の優良店を紹介するサイト
 FANZA新着動画
特選素人娘マル秘動画
FANZA新着動画
特選素人娘マル秘動画
-

【4K】シン・素人マスク 33歳人妻Kカップマゾメス 西村…
-

【4K】シン・素人マスク 22歳女子大生Hカップマゾメス …
-

「推しは推せる時に●せ!」セクハラ、●撮、生中●要 クズマ…
-

巨乳ショートカットエロすぎる美女H Part.1
-

エロコス爆乳すぎる豊満色白美女 Part.2
-

エロコス爆乳すぎる豊満色白美女 Part.1
-

高身長で美人の美尻と美脚でハイレグ Part.2
-

高身長で美人の美尻と美脚でハイレグ Part.1
-

おばさんが餌食に!上司のたわわな爆乳に超勃起!