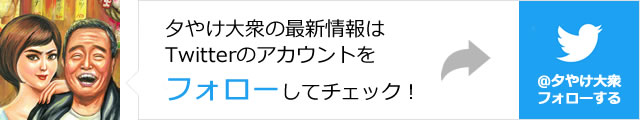Catch Up
キャッチアップ
Catch Up
キャッチアップ

この官能小説は、現在50代から60代の方々の若かりし時代を舞台背景にしています。貧しかったけれど希望に満ち溢れていたあの頃、そこには切なくも妖しい男と女の物語が今よりも数多く存在しました。人と人とが巡り合う一瞬の奇跡、そこから紡がれる摩訶不思議な性の世界をお楽しみください。 編集長
【留年大学生を男にした下宿屋の女将】長月猛夫
1966年、4年後にひかえた万国博覧会をもくろんで、大阪の町は活気にあふれていた。
そのころ高木が暮らしていた場所は、通天閣の建つ新世界の近く。労務者の町、あいりんにも目と鼻の先で、飛田新地も間近にある。
そんな下町で、高木は24歳になっていた。
気弱で人見知りが強いということも手伝って高木には女友だちがなく、しかも童貞。そのうえ2回留年していたので、まだ学生の身分だった。
国立大学の文学部に席をおいていたものの、なにを学ぶ気力もなく、高木は悶々とした日々を過ごしていた。そして夏季休暇に入ると、帰省でだれもいなくなった下宿に高木は一人残された。
扇風機がカタカタ鳴る狭く散らかった部屋で、高木は創刊されて間もない「平凡パンチ」や「プレイボーイ」のグラビアを見たり、ぬるいトリスを飲んで酔っ払ったり、そんなだらけた毎日を送る。
「まだ、お家には帰りはれへんのですか?」
高木の下宿はまかないつきで、3度の食事は女将の多恵が用意してくれた。その多恵が昼食をとりに食堂へ来た高木にいう。
「ご両親、ご心配しはりますよ」
「ええんです、帰ってもしんどいだけやから」
高木はスネた声で答える。
「しんどい? おだやかとちゃいますね」
多恵の年齢は44歳。高木とは20歳離れていた。
清楚で華麗、肌の色は白く、いつも着物を身につけ、上品な化粧をほどこしている。そして高木のような学生にも、きれいな敬語で接していた。
すきのない高貴な仕草と立ち振る舞い。多恵は、そんな雰囲気を持つ女性だった。
「ごちそうさま」
暑さと酒で身体がまいっていた高木は、半分も食べずに席を立つ。
「もうよろしいの」
多恵の言葉に高木は何も答えず、ふらつく足で自分の部屋へと向かった。
何かにいらだち、あらゆる物に不満をいだいていた。それでいて、何にいらだっているのかがわからない。不満をどうすれば解消できるのかもわからない。
そんな若い夏だった。
部屋に戻り、高木は横になってぼんやりと窓の外をながめる。狭く切り取られた空は真っ青で、いつのまにか故郷の空を思い出す。
高木が生まれたのは、本州の最南端に近い小さな漁村だった。
眼前に広がる広い海、真っ青な空、そびえる緑濃い山々。村に住むほとんどが漁業で生計を立てていて、中学を卒業してすぐに仕事に就くものが多い。
そんな村から高木は数年ぶりに大学に合格。しかも進学先は大阪の国立一期校だ。村中の期待を受け、電車に乗って故郷をあとにするときは、駅で総出の見送りを受けた。
それから6年が過ぎていた。
「オレ、こんなとこで、いったい何やってるんやろ」
そしてこれから、どうなってしまうんだろう。その言葉を口に出してしまうと、筋肉の突っ張る不安に駆られる。将来を思えば思うほど、胃液の噴き出しそうな焦燥で身が震える。
高木は身を起こし、半分空になったトリスのボトルに手をのばした。
「すいません、入ってかまいません?」
そのとき、部屋の前から多恵の声がした。
「はい」
高木は座ったままで返事をする。扉が開き、多恵は静かに入ってくる。
「またお酒。昼間から」
ボトルを手にした高木を見て、多恵はとがめた。
「なんか、用ですか」
ぶっきらぼうに高木はたずねる。
「さっきの言葉やけど」
多恵は、散らかった部屋にわずかなスペースを見つけて座った。
「帰ってもしんどいだけって、どういうことですのん?」
「別に、たいしたことちゃいます」
「聞きずてなりまへん。ほかの学生さんは、みなさんうれしそうに帰っていきはんのに」
「学生いうても落第生。どんな顔して帰れると思います」
「そんなん、親御さんには関係ないんと違います? どんな生き方してても親と子。顔を見たいに違いありません」
「女将さんは、なんにも知らんからいえるんや。村の人間、ほとんどが見送ってくれた。それが落第して、しかも将来何をしたいかも決まってない。そんな人間がふらりと帰っても親は迷惑するだけや」
高木の半ばいきどおりがふくまれた言葉を聞き、多恵は黙ってしまう。高木は多恵から目線をはずしつつも、その姿を横目でながめた。
敷きっぱなしの万年床、散らかった雑誌とウイスキーのビン、ごみ箱からあふれているチリ紙の山。
そんなむさ苦しい男の部屋に座る多恵の姿は、まさに掃きだめのツルそのものだ。
きちんとゆわえられた髪、長い首、白いうなじ。吐く息や立ちのぼる甘い香りが、周囲の空気すら彩に染めてしまう。
多恵は、わざと顔をそむける高木にたずねた。
「ほな、お聞きしますけど。なんのために大学生になりはったんですか? ご両親のため? 村のため?」
「いいえ、ボクは作家になりたかったんです」
「ほなら、その夢かなえはったらどうです?」
「ダメなんです。書かれへんのです」
「なんで?」
「書いても、書いても満足でけへん。人に見せるのが恥ずかしい」
「それやったらいっぺん、ウチに見せてください」
「だめです、恥ずかしい」
「なにが恥ずかしいの?」
「自分でも満足でけへんもん、人に見せることなんかでけへん」
「そやから……」
「もうええ! ボクのことはもうエエから、出てってください!」
高木はついつい声を荒らげてしまった。多恵はしばらく、うなだれる高木の横顔を見つめていたが、何もいわずに立ちあがる。
それでも多恵は高木に何かを告げようとした。が、言葉をつむぐのがはばかられたのか、黙ったままで部屋を出た。
夜、高木は食堂には赴かなかった。何も食べず、部屋の中に転がっている。
日が暮れ、室内に闇が迫る。明かりもともさず、ただ天井を見つめる。
開け放たれた窓からは、ぬるい風と繁華街の喧騒がただよってくる。となりの家の屋根の上に、ネオンのともった通天閣が見える。
頭の中で何かを考えているはずなのに、混乱した思考は結果をもたらしてくれない。そのうち何を考えていたのか、何を考えるべきなのかもわからなくなってくる。
「高木さん、お食事お持ちしましたけど」
扉の向こうから、多恵の声が聞こえた。高木は声を認識したものの、身体を動かす気力がわかない。
「入ります。かましまへんわね」
多恵は食事の乗った盆をいったん廊下におき、扉を開けて部屋に入ってくる。
「電気もつけんと……」
多恵は蛍光灯からぶらさがるひもを引く。白い光が満ち、高木はまぶしそうに顔を手でおおう。
テーブル代わりのミカン箱の上に、多恵は料理を並べた。
「お昼間、ウチいい過ぎました。ごめんなさい」
並べ終えた多恵は正座し、高木に向かって頭をさげようとする。
「や、やめてください」
そんな多恵を、高木あわてて止めた。
「声を荒らげてしまったのはボクです。女将さんには感謝しきれないくらいお世話になっておきながら……」
高木は、それでも頭をさげようとする多恵の肩を抱き、顔をあげさせた。それと同時に、高木と多恵の視線が重なり合う。
多恵のひとみは妖しさに満ちていた。高木は、そんな多恵の眼差しに心の動揺をしてしまう。
「高木さん」
「は、はい」
「自分の小説を、人に見せるのが恥ずかしいっていわはりましたよね」
「はい」
「それは、ウチにも? ウチにも見せられへん?」
「はい」
「ほな、ウチが高木さんに恥ずかしいもんを見せたら、読ませてもらえますか?」
言葉の意味がわからない。多恵が交換条件を示してきたのはたしかだが、彼女が小説などの創作物を手がけているわけではないだろう。
「恥ずかしいもん?」
「そう」
「それは、なんですか」
「約束してくれます?」
「ええ、まあ……」
高木はあいまいな言葉を返す。すると多恵は立ちあがり、するすると着物の帯をときはじめたのだった。
着物を脱ぎ、多恵は長じゅばん姿になる。
「恥ずかしい」
うつむいて顔をそむけ、やがて多恵は裸身をさらした。
「ウチの裸なんか、みっともないだけやけど」
両腕と脚を交差させて乳房と陰部をかくす。そんな多恵の姿を見て、高木は言葉をなくした。
グラビアに登場するモデルのような、若く張りつめた美しさはない。しかし、安っぽい蛍光灯の光の中に浮かぶたおやかな肉体は、妖艶で幻を見ているような感覚を高木にあたえる。
腕で押さえつけられ、深い谷間をつくる胸乳。わきから太ももにかけての曲線が艶かしく、腰から下の張り出しはささやかだ。長い脚はほどよく実り、全体をおおう贅沢な脂が柔軟で輪郭を形づくっている。
高木は畳に腰をおろしたまま目を見開き、ぼんやりと口を開けて多恵の裸体を見つめた。
「これでよろしいやろ、そやから……」
多恵は身を折り、畳に落とした衣装を拾おうとする。そんな多恵に、高木は飛びついてしまった。
「なに、なにしはんの!」
押し倒された多恵は、抵抗する。
「女将さんが悪いんや、女将さんがボクに……」
おおいかぶさった高木は、多恵の両腕をはらいのけ、その肢体をまじまじと見つめた。
豊満な乳房に色づいた乳首。透き通った純白の肌は、しっとりとした汗がにじみ出している。股間の茂みは薄く、恥丘がこんもりと盛りあがっている。
「ひょっ、ひょっとして高木さん、女、知りはらへんの?」
押さえつけられ、あお向けになった多恵はいう。高木は黙ってうなずく。
「そう、そやからあんなこというんやわ」
「あんなこと?」
「自信がない、なんてこと。男さんは、女知ったら自信持つもんです」
「そう……」
「そうです、男さんは女知って一人前の男になるんやから」
「ほ、ほな、ボクに……」
高木は多恵の上におおいかぶさりながら、承諾を得るように目を見た。
「ウチみたいなオバちゃんでエエの? 若い女の子と違てええの? 一生に一度のことやのに後悔せえへん?」
高木は首を縦に振った。それを見て多恵は妖艶な笑みを浮かべていう。
「その前に」
「その前に?」
「窓閉めて、電気消して」
高木は大あわてで窓を閉め、蛍光灯を消す。ふたたび闇が部屋の中に充満する。それでも多恵の肉体は、白くぼんやりと浮かびあがる。
高木は服を脱いだ。多恵は高木を見つめながら、ゆっくりと両脚をひろげた。
「誤解せんといてね。だれとでもこんなことする女とは……」
「わかってます、信じてます」
高木は、そうつぶやいて唇を重ねる。
乳房に手をまわすと、世の中にこれほど心地よいものが存在するのか、と思えるほどやわらかい。力を込めた指は、すんなりと食い込んでいく。
多恵は高木の右手を取って、自分の秘部にいざなった。
「ここ、ここに……」
薄く目を開けたまなざしが向けられる。泣き出しそうでもあり、期待を込めているようでもある。
多恵の部分は、しっとりとした潤いに満ちている。指の先を入れると、ぬるみと熱と肉の感触が伝わってくる。
高木は屹立した肉柱で、多恵のとば口を狙った。しかし、どこに挿入していいのか、先端の感覚だけではわからない。
多恵は、そんな高木に手を添え導く。
「そ、そのまま、腰に力入れて」
高木は多恵の誘導にしたがい、グイと腰を押しつけた。
「あ……、あん」
刹那にしてまとわりついてくる肉襞。筒内はかすかな痙攣をくり返し、高木をすっぽりと包み込む。温かくぬめった圧力が高木を締めつけ、包皮に蜜が染み込んでいく。
高木はゆっくりと抜き差しをはじめた。歓喜が怒涛のように迫ってくる。精液だまりが極限にまで膨張し、数億の精子が外に出たいと暴動している。
「だ、ダメだ。ダメです」
「いい、いいのよ、そのまま」
「いいんですか」
「いいの、出してもいいのよ」
我慢は限界を超えた。高木は夢中になって抽送をくり返し、そのまま多恵の中にほとばしりを放ったのだった。
初めてだから仕方ない。多恵は、そういって慰めてくれた。
「けど、もういっぺんできますよね」
多恵はしぼんだ高木を、前かがみになって口にふくむ。舌の絡まりと唾液の粘。内ほほの刺激と吸い込みの力で、高木はすぐに復活する。
「今度は、ゆっくりとウチを召しあがって」
いたずらな笑みを浮かべた多恵は、高木の上に馬乗りになり、自ら膣内へと納めていった。
その後、高木は多恵に溺れ、何度も身体を求めた。彼女も二人きりしかいない下宿の中で、高木の求めに応じる。夏が終わるまで、高木と多恵は寝食を忘れるほどに没頭した。
やがて、言葉や行動、肉体による多恵のはげましもあり、自信を持った高木は、ようやく納得できる作品が書けるようになる。それを多恵が読んで批評し、何度か新人賞にも応募した。
しかし結果がわかる前に夏は過ぎ、ほかの学生たちが戻ってくると、二人の関係も終わりを告げた。
秋が来て、冬が来る。文学賞を獲得する夢はかなわなかったが、単位を修得できた高木は卒業が決まり、多恵の下宿を出ることになった。
「高木さん。がんばってくださいね。きっと作家さんになれる。そのときはウチにも連絡くださいね。楽しみに待ってます」
別れ際、多恵は高木に告げる。
「もちろんです。約束します」
「また、いつでも遊びにきてくださいね」
「はい、いつか必ず」
高木はいい残して、下宿をあとにした。
卒業後、高木は故郷に戻ることなく、大阪の地で教員になった。そして、社会人ゆえの多忙さもあって小説を書く時間がとれず、作家の夢を断念する。
多恵の下宿屋をたずねることもなかった。
高度経済成長期に入り、まかないつきの下宿屋は時代にそぐわないのか、軒並みアパートかマンションに姿を変えていった。
教員生活にも慣れた高木は、久しぶりに新世界をおとずれ、多恵の下宿屋をたずねてみる。だが、そこには新築のアパートが建っているだけだ。
「約束、守られへんかったな」
高木は、そうつぶやき、背中を丸めて繁華街に向かって歩きはじめたのだった。
- 【長月猛夫プロフィール】
- 1988年官能小説誌への投稿でデビュー。1995年第1回ロリータ小説大賞(綜合図書主催)佳作。主な著作『ひとみ煌きの快感~美少女夢奇譚』(蒼竜社)/『病みたる性本能』(グリーンドア文庫)/『19歳に戻れない』(扶桑社・電子版)ほか。
この記事の画像
関連キーワード
 Linkage
関連記事
Linkage
関連記事
-

昭和官能エレジー第32回「夏休みの幻 廃屋の女」長月猛夫
-

昭和官能エレジー第31回「年上少女の誘惑」長月猛夫
-

昭和官能エレジー第30回「女になれずに逝った少女」長月猛夫
-

昭和官能エレジー第29回「惑乱された父親の愛人」長月猛夫
-

昭和官能エレジー第28回「教え子の母の誘惑」長月猛夫
-

昭和官能エレジー第27回「緊縛をせがんだ淫乱少女」長月猛夫
-

昭和官能エレジー第26回「下宿住まいの浪人生と自殺願望の女…
-

昭和官能エレジー第25回「生板本番ストリッパーと屈辱の照明…
-

昭和官能エレジー第24回「夜桜凌辱の艶躍」長月猛夫
-

昭和官能エレジー第23回「母親に売られた18歳」長月猛夫
-

あの週刊大衆が完全バックアップした全国の優良店を紹介するサイト
 FANZA新着動画
特選素人娘マル秘動画
FANZA新着動画
特選素人娘マル秘動画
-

個撮ナンパ #清楚で初心だと思ったら男好きな隠れビッチ女子…
-

いつでもドコでも即フェラ密着パイズリ4hours
-

毎日違うおっぱいに責められたい… 日替わり巨乳痴女SEXカ…
-

月野江すい プレミアムステージ初BEST8時間
-

「柔らか谷間に何度も出しなさい!」 射精直前の超快感パイズ…
-

奇跡の乳を持つ最胸シロウト 清原みゆう S1デビュー 1周…
-

男なら一度は抱きたい!高級ラウンジ嬢の超イイ女達とハメまく…
-

人妻自宅サロンBEST 底辺クズ隣人の汚らわしいデカマラに…
-

世界クラスのグラマラスボディ 気品溢れ出る本物CA 武田怜…