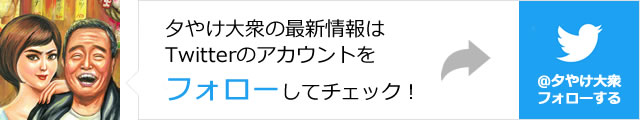Catch Up
キャッチアップ
Catch Up
キャッチアップ

この官能小説は、現在50代から60代の方々の若かりし時代を舞台背景にしています。貧しかったけれど希望に満ち溢れていたあの頃、そこには切なくも妖しい男と女の物語が今よりも数多く存在しました。人と人とが巡り合う一瞬の奇跡、そこから紡がれる摩訶不思議な性の世界をお楽しみください。 編集長
【深夜ラジオのメッセージと再会】長月猛夫
「それでは次のお便りです。ラジオネームは春待ちの白梅さん。きれいなお名前ですね」
深夜0時、高校3年の博隆は、机に向かって鉛筆を走らせながらラジオを聴いていた。
テレビは茶の間に鎮座している。観るのは家族のそろう夕食時だけだ。しかも番組はチャンネル権を持つ父親が選ぶ。
来月に受験を控えた博隆は食事を終えると、すぐに勉強部屋にこもる。楽しみにしているのはラジオの深夜放送。軽快なDJのしゃべりと流行の音楽に耳をかたむける。
「白梅さんは22歳の女子大生。それでは、メッセージを紹介します」
番組ではリスナーの投稿が読まれ、なかにはハガキ職人と呼ばれる常連もいる。博隆は投稿こそしていなかったが、同世代の意見に同意したり、ユニークな内容に笑ってみたり、ときには違和感をおぼえたりしていた。
「こんばんは。いつも楽しく聞いています。じつはわたし、いますごく会いたい人がいるんです」
女子大生のハガキが読まれる。どうせただの恋愛話だろう、と博隆はあまり興味を持たない。しかし話が進むにつれ、博隆は思わず手を止めてしまった。
「その人の名はヒロタカさん。わたしはヒロくんと呼んでいました。4つ年下のヒロくんは、以前住んでいた家のとなりに住んでいて、まるで弟のような存在でした」
幼いころは近所の友だちと一緒になって遊び、高校受験のときには家庭教師も買って出た。無事、高校に合格した年の夏に引越ししてしまったが、いまでも彼のことが忘れられない。
「わたしは大学を卒業すると、親の決めた人と結婚します。その人はやさしくて、仕事もお父さんが経営する会社に勤めています。なんの不満もないのですが、一言ヒロ君にいっておきたいことがあるんです。だから、この放送を聴いていたら、会いにきてほしいんです」
「まさか……」
博隆は、思わずつぶやいてしまった。
「佳子姉ちゃん」
博隆は、机のかたわらに置かれたトランジスタラジオを見つめる。DJはハガキを読み進め、最後に投稿主の示す場所と日時を伝えて締めくくった。
博隆の隣家には、佳子という女の子が住んでいた。お互い一人っ子ということもあり、二人は姉弟のように仲がよかった。とくに佳子は何かと博隆の世話を焼き、遊びに出かけたり、小学校を卒業するまでは一緒に登校したりもしていた。
博隆が中学生になると、佳子は高校2年生。さすがに遊ぶことはなくなったが、顔を合わせれば世間話もするし、下校途中に出会えば並んで帰宅することもあった。
佳子は成績がよく、とくに英語を得意としていた。反対に博隆は英語がまったくダメ。3年生になって高校受験を控えても、英語が足を引っ張って、志望校の合格は覚束ない状態となる。
「じゃあ、わたしが教えてあげる」
すでに大学生となっていた佳子は、土曜日の午後と日曜日に、博隆の家に通うようになる。その甲斐があってか、博隆の成績はあがり、春には無事、志望校への進学が決まった。
合格発表の日、博隆は佳子と近所の公園で待ち合わせる。春はまだ浅かったが、陽光はうららかなきらめきを放ち、風が芽吹きの香りを運んでいた。
「佳子姉ちゃん、合格したよ!」
その言葉に佳子は飛び上がらんばかりのよろこびを示し、博隆の目を見つめて両手を握る。その、やわらかくてかすかに冷たい感触に、博隆は圧迫される胸の苦しみをおぼえた。
「おめでとう」
「ありがとう。佳子姉ちゃんのおかげだ」
「ううん、ヒロくんががんばったから。そうだ、お祝いしなくっちゃ」
「いいよ、そんなの」
「ダメ。ヒロくん、目をつむって」
いわれるままに、博隆は目を閉じた。その瞬間、やわらかな感触が唇に伝わる。
驚いた博隆は目を開けた。眼前には佳子の表情が間近にあり、自分の唇を博隆の唇に押し当てていた。
「ごほうび」
顔を離したとき、佳子ははにかんだ笑みを浮かべていう。
遠くで鳥の啼く声がひびく。公園の隅には、白い梅の花が芳しい香りを散らしながら咲き誇っていた。
ラジオのDJは日時こそ明らかにしたものの、場所については「思い出の場所」としか告げなかった。ハガキにそう書かれていたのか、野次馬が集まるのを危惧してぼやかしたのかはわからない。しかし、博隆には心当たりがある。
「きっと、あの公園だ」
とはいえ、投稿した女子大生が佳子かどうかは確信が持てない。
ヒロタカという名前の人間など、日本には数多いるだろう。しかし、4つ年上で、となりに住んでいて、高校受験のために家庭教師をして、高校を合格した夏に引越しをするという条件は整いすぎている。
「佳子姉ちゃんかぁ」
博隆は椅子の背もたれに身体を預け、ぼんやりと天井に視線を向けた。
中学1年の5月、下校途中の博隆は、やはり学校帰りの佳子と出くわした。季節にしては暖かな日だった。
「きょうは暑いわね」
そういって佳子は、はおっていたカーディガンを脱ぐ。その姿を見て、博隆の胸はときめいてしまった。
カーディガンの下は白い長袖のブラウスだ。素肌が見えているわけでもない。それでも、「脱ぐ」という行為に心が揺らぐ。と同時に、ブラウスの胸元の盛りあがりや、首を振ったときにたなびく髪、ほのかに伝わる甘酸っぱい香りに翻弄されそうになる。
このとき初めて、博隆は佳子に異性を感じてしまった。
その後、佳子は歳を重ねるにつれ、少女から大人へと成長していく。大学生になった佳子が家庭教師をするといったとき、博隆はあわい期待をいだいてしまったほどだ。
「けど、いいたいことって……」
指定された日は3日後、時間は午後5時だ。授業を終えて駆けつけても十分に間に合う。
引越しの日、佳子は寂しい笑みを浮かべていた。その表情が、ぼんやりと博隆の視界に浮かんでいた。
その日、そわそわした気分で過ごしていた博隆は、下校時刻になると足早に公園へ赴いた。
年が改まって半月ほどたった日の午後、空は雲ひとつなく晴れわたっているが、空気は冷たく、生垣の山茶花だけが風景に彩りをそえていた。
「あ……」
まだ5時には20分ほど余裕はあったが、その人はすでに到着していた。
ベージュ色のコートに身を包み、ベンチに腰をかけている。とはいえ、それが佳子かどうかは判断がつかない。
博隆ははやる気持ちをおさえて、ゆっくりと歩を進める。すると博隆に気配に気づいたのか、女性は長い髪を揺らして身をよじった。
「ヒロくん?」
「佳子姉ちゃん?」
「ヒロくんだ、きてくれたんだ」
佳子は立ち上がり、小走りで博隆に近づいた。
「お久しぶり、お元気?」
「うん」
「ラジオ、聞いてくれたんだ」
「うん」
むかしの面影を残しながらも、佳子は完全な大人の女性だった。
肩より長く伸ばされた黒髪は少しウェーブがかけられ、まぶたにはアイシャドー、唇に朱色のルージュが塗られている。耳たぶにはイヤリング、首にネックレス、手首には細い腕時計。
そんなきらびやかな装いの佳子は、博隆の手を握ってベンチへ誘った。
「ヒロくん、もうすぐ受験でしょ。忙しいときにゴメンね」
「うん、大丈夫。息抜きも必要だし」
「どこを狙ってるの?」
博隆は志望する私立大学の名をあげる。
「国公立は?」
「数学が苦手だから共通一次は受けなかった」
「英語と国語と社会で勝負」
「うん、でも」
「でも?」
「相変わらず、英語も苦手」
「もう、せっかくあれだけ教えてあげたのに」
佳子は苦笑を浮かべる。
会話を交わしながら、博隆には気がかりなことがあった。それは、佳子が自分に伝えたいという言葉だ。だが、自分から聞き出すのもはばかれる。
「もうすぐ3年になるのね」
佳子はポツリという。
「この公園でヒロくんから合格の報せを聞いて」
「うん」
「あのときのこと、おぼえてる?」
博隆の表情をのぞき込む佳子。博隆は羞恥で、思わずうつむいてしまう。
「ごほうびっていったけど、本当は違う意味もあったんだ」
「え?」
「ふふふ」
佳子は意味ありげに笑った。
黄昏が迫り、冷気がじわじわと染みこんでくる。風が二人を包み込むように舞い、佳子はコートの襟を立てた。
「寒いね。わたしね、きょう1泊する予定なんだ」
「そうなんだ」
「駅前のホテルに部屋を取ってるの。話の続きは、そこにしない?」
佳子は博隆を注視する。そのひとみには、博隆のみぞおちをうずかせる妖しさが影を落としていた。
暖房のよく効いたシングルルーム。佳子はコートを脱いでクローゼットにしまう。ひざより少し短い黒いタイトスカートに、上半身は白いセーター。胸元は大きなふくらみを誇示している。
そんな佳子をながめながら、詰襟姿の博隆は立ちすくんでいた。
「ヒロくん、ここへ」
ベッドに腰かけた佳子は、博隆をとなりにいざなった。
博隆が座ると、佳子は距離を縮める。佳子のオーラに包まれ、博隆は緊張にさいなまれる。
「ヒロくん、ラジオ聞いたんなら、わたしが会いたかったわけも知ってるんでしょ」
「うん」
「なんだと思う?」v
「え?」
「言いたかったこと」
博隆は言葉をつむぐことができない。
「わたしね、今年の6月に結婚するの。相手は将来、社長になることが決まってるし、性格もやさしいハンサム。でも、それでいいのかなぁって」
「どうして?」
「だって社会人の経験もなしで主婦になっちゃうし、それに……」
佳子は博隆の目を見つめる。反り返ったまつ毛、切れ上がった目尻。黒目がちな眼球が潤んでいる。
「わたし、好きな人がいるの。それはね、ヒロくん」
「……!」
博隆は動揺を隠せないでいた。
「ヒロくんのことは、ずっと弟みたいに思ってた。けど、ヒロくんが中学生になって、どんどん男らしくなってくると、違った感情が生まれてきた。ねえ、おぼえてる? ヒロくんの部屋で勉強を教えているとき、おっぱいがヒロくんのひじに当たったの」
「う、うん……」
机に向かう博隆のとなりで、佳子はアドバイスをする。ノートの答えが間違っていれば、身を乗り出して訂正する。そのときに、胸乳が博隆のひじや二の腕に当たることもあった。
「ヒロくんのアソコ、大きくなってたの、知ってるのよ」
佳子は艶然とした笑みを浮かべた。
「二人きりなんだから、遠慮しなくてもよかったのに。そう思ったけれど、ヒロくんはまだ中学生だったし。だから、大人になるまで待とうって。でも、わたしは引っ越してしまった。サヨナラはつらかったなぁ」
「それは……」
自分も同じだといいかかけて、博隆は口をつぐんでしまう。
「いいたかったことは、これだけ。でも、したいことはあるの」
「したいこと?」
「ヒロくんが大人かどうか、たしかめたい。大人じゃなかったら、わたしが大人にしてあげたい」
佳子は視線をはずさない。その目線に吸い込まれ、博隆も佳子を見つめてしまう。
「ねえヒロくん、キスして。あのときみたいに。ううん、あのとき以上に」
佳子は目を閉じて唇を突き出した。博隆は苦しいほどの胸の高まりをこらえながら、佳子の唇をふさいだのだった。
口づけを交わしながら、佳子はベッドに横たわり、博隆はおおいかぶさる形となる。佳子は博隆の腕を取り、自分の胸に押しつけた。
着衣の上からでもはっきりとわかるボリュームと柔軟さ。顔を離した博隆を見て、佳子は薄い笑みを浮かべる。
「初めてなんだ。手が震えてる」
博隆は何も答えられない。
「じゃあ、教えてあげる。わたしが大人にしてあげる」
態勢を入れ替え、佳子が博隆にかぶさった。
佳子は自分でセーターを脱ぎ、ブラジャーをはずす。露出された乳房を見て、博隆は目を見張ってしまう。
形よく盛りあがった両の乳肉は輪郭が脇からはみ出し、中央にある乳首は桜色に染まっている。白い肌にうっすらと青い静脈が透けて見え、佳子が髪をかきあげる動きに合わせてプルリと揺れる。
「舐めて」
佳子は乳首を博隆に与えた。
吸いつきながら舌で転がし、ぎりぎりまで希釈した砂糖水のような甘さを味わう。佳子は博隆の上着を脱がし、ワイシャツのボタンをはずした。
胸板をむき出しにした博隆の、米粒大の乳首を舐め、佳子は身体をずらす。そして、ベッドの脇から床に下ろした博隆の脚からズボンと下着をとる。
博隆の一物は、すでに大きくとがっていた。
「ふふふ」
佳子は博隆を見つめながら、屹立した肉棒を舐め、頬張る。そして、舌を絡めて尖端をさぐると、博隆は早くも暴発してしまったのだった。
「む、んん、ん……」
口腔にそそぎこまれる精液を、佳子は口に溜めて飲み干した。
「うん、おいしい」
残汁を指に絡めてもてあそびながら、佳子は淫靡な表情を浮かべる。
「今度はゆっくりとわたしを確かめて」
そういうと佳子は立ち上がり、スカートを脱いでパンティをおろした。
博隆にまたがり、佳子は上半身を屈めて唇を重ねる。博隆は佳子の乳房に手を伸ばし、指に力をこめてめり込ませた。
柔軟ではあるが、弾き返す張りがある。手のひらでおおうと、きめ細やかな肌が吸いついてくる。
佳子は博隆の手を、股間に導く。ウネウネとした淫唇の感触と、にじみ出た蜜の潤いが指先を敏感にした。
「ここにヒロくんが入るの。わたしが最初の女になるの。それでいい?」
「うん、佳子姉ちゃんがいい」
「うれしい」
博隆の指先が、佳子の膣口にもぐりこんだ。その衝撃に、佳子はのけ反って声をあげる。
「やん、感じちゃうん!」
身を起こし、博隆に指を添え、佳子は秘裂にあてがう。そして、ゆっくりと腰をおろして内部へ誘導した。
「入った、わかる?」
「うん」
「どう、わたしの中」
「あったかくってやわらかい」
「うん、ヒロくん、どんどん大きくなる。やん、気持ちいい」
緩急を加えて佳子は身を躍らせた。博隆は佳子の膣筒を攪拌する。愛液があふれてくちゅぐちゅと音を立て、肉襞がぜん動しながら肉棒を締めつける。
博隆は自分の上で舞う佳子をながめた。髪の乱れを気にも留めず、挿入部分を見せつけるかのように腰を浮かせ、沈める。
白い肌が桃色に染まり、汗がにじんでヴェールとなる。白磁のような光沢を放ちながら、佳子はよがり、歓喜をあらわにした。
上下する乳房の質量を両手で支えながら、博隆は佳子に身をゆだねる。それと同時に、佳子をだれにも渡したくない、自分が独占したい、この快感を今日だけで終わらせたくないという思いに駆られてしまった。
「け、佳子姉ちゃん」
「なに、うん、なに?」
「一緒にいようよ、オレと一緒にいよう」
佳子の律動に合わせて抽送をくり返しながら、博隆は告げる。
「だれのものにもしたくない、オレだけの佳子姉ちゃんでいてほしい」
「だめ、やん、あ、ダメよ、それはダメ」
「どうして」
「うんん、ダメよ、あああん、気持ちいい!」
佳子は前のめりになって博隆の口をふさぐ。腰の揺り動かしは早くなり、博隆の劣情があおられる。
「あ、ダメだ、そんなにしたら……」
「イッちゃうの? いいわよ、出しても」
「このままで……」
「うん、いいの。やんやん、ヒロくん、ステキ、やああん、イッちゃいそう」
「出る、あ、で……」
博隆は佳子の中で果ててしまう。精液の注入を受け止め、佳子は幾度か痙攣し、そのまま博隆の上におおいかぶさった。
「ありがとう、ヒロくん」
博隆のとなりで天井を見つめる佳子はいった。
「わたしを自分だけのものにしたいっていってくれて」
「ダメなの?」
博隆は問い返す。
「うん、ダメ」
「好きでもない相手と結婚して幸せになれるの?」
「なれる。なってみせる」
佳子は身を起こし、ベッドから降りた。
「絶対、幸せになって見せる。そう決めたの」
恵子は博隆に背中を見せ、ホテルに備えつけのガウンを素肌にはおる。
「シャワー浴びてくる。ヒロくんは、その間に帰って」
「え?」
「苦しむのはいや。お願いだから」
博隆に背中を向けたまま、佳子は浴室に消える。その声には涙が混じっていた。
いたたまれない気持ちのまま、博隆はホテルをあとにした。
「佳子姉ちゃん」
夜空にそびえるホテルをながめ、博隆はつぶやく。
「苦しむのはオレのほうだよ」
春になり、博隆は大学へ進学した。その後の佳子については、まったく知らない。
- 【長月猛夫プロフィール】
- 1988年官能小説誌への投稿でデビュー。1995年第1回ロリータ小説大賞(綜合図書主催)佳作。主な著作『ひとみ煌きの快感~美少女夢奇譚』(蒼竜社)/『病みたる性本能』(グリーンドア文庫)/『19歳に戻れない』(扶桑社・電子版)ほか。
この記事の画像
関連キーワード
 Linkage
関連記事
Linkage
関連記事
-

昭和官能エレジー第19回「哀願をくり返した通相手の少女」長…
-

【昭和官能エレジー】第18回「仕組まれたポルノ女優――中に…
-

昭和官能エレジー第17回「別れを切り出された浅はかな男」長…
-

昭和官能エレジー第16回「童貞男子を翻弄した謎の淫乱少女」…
-

【昭和官能エレジー】第15回「女のたずねてくる電話ボックス」
-

昭和官能エレジー第14回「凌辱されたタバコ屋の女子大生」長…
-

昭和官能エレジー第13回「団地妻の淫惑」長月猛夫
-

昭和官能エレジー第12回「拾ったフィルムに映されていた緊縛…
-

【昭和官能エレジー】第11回「歌手崩れの男に溺れたご令嬢」
-

昭和官能エレジー第10回「アンパン中毒のフーテン少女」長月…
-

あの週刊大衆が完全バックアップした全国の優良店を紹介するサイト
 FANZA新着動画
特選素人娘マル秘動画
FANZA新着動画
特選素人娘マル秘動画
-

個撮ナンパ #清楚で初心だと思ったら男好きな隠れビッチ女子…
-

いつでもドコでも即フェラ密着パイズリ4hours
-

毎日違うおっぱいに責められたい… 日替わり巨乳痴女SEXカ…
-

月野江すい プレミアムステージ初BEST8時間
-

「柔らか谷間に何度も出しなさい!」 射精直前の超快感パイズ…
-

奇跡の乳を持つ最胸シロウト 清原みゆう S1デビュー 1周…
-

男なら一度は抱きたい!高級ラウンジ嬢の超イイ女達とハメまく…
-

人妻自宅サロンBEST 底辺クズ隣人の汚らわしいデカマラに…
-

世界クラスのグラマラスボディ 気品溢れ出る本物CA 武田怜…