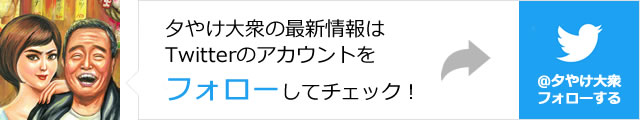Catch Up
キャッチアップ
Catch Up
キャッチアップ

この官能小説は、現在50代から60代の方々の若かりし時代を舞台背景にしています。貧しかったけれど希望に満ち溢れていたあの頃、そこには切なくも妖しい男と女の物語が今よりも数多く存在しました。人と人とが巡り合う一瞬の奇跡、そこから紡がれる摩訶不思議な性の世界をお楽しみください。 編集長
【歌手崩れの男に溺れたご令嬢】長月猛夫
「あした、この町を離れる」
美佐子は告げた。
「そうなんだ」
畳の上に寝転がり、ハイライトをくゆらしていた武田は答える。
「それだけ?」
美佐子はたずねる。
「ああ」
頭の下で腕を組み、窓に顔を向けた武田は、そう短くいった。
窓の外は雨が降っていた。ここ数日間、しとしとと降り続け、10日ほど前の残暑がウソのようだ。
「もう、扇風機もいらねえかな」
美佐子から顔をそむけたままの武田はいう。
「5年間ありがと」
「もう5年か」
「出会ったときは17だった」
「オレは二十歳だ」
「5年たってもあなたは変わらない」
「老けたよ。もうドカチンもきつい」
「学校へは戻らないの?」
「何をいまさら」
フィルターぎりぎりまでタバコを吸い切り、吸い殻が山積みになった灰皿に押し付ける。そして空色のパッケージから新しい1本を取り出すと、マッチをすって火をつける。
「止めてくれないのね」
美佐子は涙のまじった声でいう。
「止めてどうする」
武田は鷹揚のない声で告げる。
「結婚するんだろ」
「うん」
「親の決めた相手と」
「うん」
「そう決めたんだろ、美佐子が」
「うん」
「オレに何をいう権利はない」
美佐子はこらえきれず、涙をこぼしはじめた。うつむき、唇をかみ、さめざめと泣く。やがて涙は堰を切ったように流れ出し、美佐子は嗚咽をあげた。
そんな美佐子を一瞥することもなく、武田はタバコを吸い続ける。
雨はまったく止む気配を見せなかった。
5年前のその日、突然雨が降りはじめた。帰宅途中の美佐子は、小さな喫茶店の軒先に入って雨宿りをする。
「やだなぁ。傘、持ってくればよかった」
朝から曇り空がひろがってはいたものの、下校時刻までは持つと思った。しかし、予想ははずれてしまう。
校門を出て友人といっしょに歩いていたときまで、雲の切れ間からかすかに青空も顔をのぞかせていた。だが、別れたとたんに雨粒がぽつぽつと落ち出し、やがて本降りとなってしまう。
白いセーラー服が濡れ、半そでから伸びた腕を美佐子はハンカチでぬぐう。新学期がはじまって、まだ10日足らず。まだ夏の暑さがかすかに残されてはいるが、雨は素肌から熱を奪い、じんわりとした冷たさを染み込ませる。
「はやく止まないかなぁ」
腕を組み、寒さをこらえながら空を見あげ、美佐子はつぶやく。そのとき喫茶店のドアが開いて一人の男が姿を見せた。それが武田だった。
すり切れた裾が地面をこするようなジーパンをはき、肩まで伸びた髪はボサボサ。ギターケースを背負い、火のついたタバコを咥えた武田は、美沙子の姿を見て怪訝な表情を浮かべる。
背が高く、痩身の武田を見て美佐子は恐れをいだいた。緊張と恐怖で身がこわばり、それでも軽く会釈をしてしまう。
「雨じゃん」
武田はそういうと、いったん店に戻る。次に出てきたときは手に傘を持ち、それを美佐子に差し出した。
「ほら」
「え?」
「ほら」
武田は躊躇する美佐子へ、強引に傘を渡す。
「風邪ひくなよ」
そう言い残して武田は雨の中を駆け出す。
「あ……」
美佐子は武田の後姿を見送り、しばらくその場に立ちすくんでいた。
翌日、借りた傘を返そうと美佐子は喫茶店を訪れる。しかし、まだ17歳の美佐子にとって、一人で店に入るのは、かなり勇気のいる行動だった。
父親は会社のオーナー経営者。曾祖父の代から続く老舗企業だ。通っているのは私立の有名女子高。小学校からエスカレーター式で大学まで進むことができる、屈指のお嬢様学校だった。
そんな環境で育った美佐子は、喫茶店どころかデパートやスーパーも一人ではいったことがない。とくに喫茶店は、よからぬ輩が立ち寄る場所というイメージが強い。
「傘を返すだけ。うん、借りたものはちゃんと返さなくっちゃ」
美佐子は自分にそう言い聞かせ、重厚な木製の扉をゆっくりと開けた。
店内は狭く、窓もなくて闇がひろがっている。美佐子が足を踏み入れると、数人の客が視線を向ける。
緊張をおぼえつつ、美佐子は店の人間をさがした。すると、ひげを生やして丸眼鏡をかけたエプロン姿のマスターが、美佐子に近寄ってきた。
「お一人?」
「え、あ、はい」
「そこの席が空いてるよ」
「いえ、あの……」
「さ、どうぞ。そろそろはじまるから」
マスターは店の隅のボックス席を美佐子に示す。自分は客じゃない。そう伝えようとしても、言葉をうまくつむぐことができない。ただ、立ちつくしているのもばつが悪いので、美佐子はソファー席に腰をおろした。
「注文を取りにきたときにいおう」
そう思いながら、美佐子はマスターを待つ。
店の奥には脚の高いスツールが置かれ、そこだけスポットライトが当たっていた。椅子に座っているのは、ぼさぼさの髪に裾のすり切れたジーパンをはく男。
「あ、あの人」
ギターをかかえ、チューニングをするのは、美佐子に傘を渡した武田だった。
美佐子は傘を持って立ちあがろうとする。それとほぼ同時に、チューニングを終えた武田はギターの弦をつま弾きはじめる。タイミングを逃した美佐子のところに、マスターが水の入ったグラスを持って訪れ、テーブルに置いた。
「ご注文は?」
「え、あ、あの……」
「なに飲むの?」
「え、じゃあ、ジュース」
マスターは立ち去る。美佐子は財布を取り出し、中身を確かめる。そこには500円札と10円玉が数枚。
「足りるよね」
不安と緊張にさいなまれる美佐子。
「祭りの、あとの淋しさが、いやでも、やってくるのなら……」
ギターの音色に混じって、武田の歌声が聞こえてきた。哀愁の漂うしゃがれ声。それは、美佐子が今まで耳にしたこともない歌声だった。
武田の歌がすべて終わったとき、美佐子は勇気を振り絞って近寄った。
「あ、あの、これ」
震える声を出し、美佐子は傘を差しだす。
「あ、ああ」
武田は美佐子を見て、不愛想にいう。
「こんなボロ傘、返さなくてもよかったのに」
「いえ、それは」
「マスター」
武田はマスターを呼ぶ。
「はい、きのうもらった傘」
「なんだ、お前がさして帰ったんじゃないんだ」
傘を手渡されたマスターは、笑顔を浮かべて美佐子を見た。
「お嬢ちゃん、感心だね。ありがと。お礼にジュースはおごりにしとくよ」
「いえ、お礼をいうのは……」
「こんな店に一人で来るの、根性がいっただろ。その勇気に対するお礼だよ」
マスターは言い残して、傘を持って店の奥に消える。
「あ、あの……」
美佐子は武田に声をかける。
「ん? まだ、なに?」
「あの、最初に歌った曲。なんていう曲ですか?」
「ああ、吉田拓郎の『祭りのあと』だよ」
「寂しいけれど、心に残る曲でした」
「ふ~ん」
武田は興味深そうな表情で美佐子を見る。
「よかったらさ、また聞きにきてよ」
武田は美佐子に店のマッチ箱を手渡した。
「木曜日と金曜日に、ここで歌ってるから」
それから数回、美佐子は武田の歌を聞きに店をたずねた。武田は美佐子が来ているのを知ると、最初に『祭りのあと』を歌う。
武田は大学に籍を置いていた。マスターを交えてかわすステージ後の会話で知る。
「けどさ、こいつ留年決定なんだぜ」
マスターは嘲笑を浮かべていう。
「いいんだよ、大学なんかいつでも辞めてやる。オレが東京に来たのは大学が目的じゃねえ。歌を歌いたかったからだ」
「ご地元では難しいんですか?」
「無理、無理。田舎じゃデビューなんて夢のまた夢だ」
最初は怖そうな男だと感じた武田への印象が、次第に変わってくる。
武田は美佐子に夢を語った。いつかはデビューを果たし、プロのミュージシャンとして世間に自分のメッセージを伝える。
「腐った世の中をさ、オレの歌で変えてやるんだ。ディランのように」
「ディラン?」
「ボブ・ディランだよ。知らないの?」
「はい」
幼いころから、美佐子はピアノを習ってきた。音楽といえばクラシックしか知らない。自宅でテレビは見られても、歌謡番組は禁じられている。
「プロテクトソングっていって、歌詞にメッセージを乗せるんだ。ボブ・ディランは、その第一人者。やつの歌詞はすげえんだぜ。ノーベル文学賞ものだ」
「歌でノーベル賞は無理だよ」
マスターが口をはさむ。
普段は寡黙な武田だが、歌のこととなると饒舌だった。そんな、いままで知り合ったことのない年上の男に、美佐子は次第に惹かれていく自分を知った。
美佐子が喫茶店に通う回数は増えていく。ジュース代は武田がおごってくれた。多少、成績には影響したものの、留年するほどでもないし、受験の必要がないので問題にならない。
やがて美佐子は高校を卒業し、系列の女子大へ進学した。
高校時代と違い、大学生になると他校の男子と知り合うきっかけも増える。だが、美佐子は同年代の男子に興味を持つことができない。
だれもがスマートで、ほとんどが将来の暮らしが決まっている。夢を語らせても、おざなりのものばかり。武田の持つ、マグマのような煮えたぎる熱量が感じられない。
狭くて暗い店の中で、武田は古ぼけたギターをかかえて歌った。ときにはやさしく、ときには髪を振り乱して世間に対する怒りをあらわにする。
しかし、事件は起きた。
「なんだよ、しみったれた曲ばっかし歌いやがって。これからはロックだよ。ロックンロールだ!」
革ジャンに身を包み、髪の毛をリーゼントに固めた男たちが声をあげる。場違いな連中は酒に酔い、武田に対して罵声を浴びせる。
怒りをむき出しにした武田は、刹那に立ちあがろうとしたが、マスターに押しとどめられる。
「お客さん、ほかの客に迷惑だ。ロックがよければ、聞かせてくれる店に行ってくれ」
そう告げたマスターに、連中に一人が胸ぐらをつかんで押し倒した。
「キャ!」
押し倒されたマスターは、勢いで美佐子の上に転がってしまう。
「何すんだよ!」
武田は連中に食ってかかり、その中の一人を殴り倒してしまう。
「この野郎!」
別の男がナイフを取り出し、武田の右腕を刺した。
「警察だ、警察を呼べ!」
「いや、先に救急車だ!」
店の中に怒号が響き渡り、客の一人がピンク色の公衆電話の受話器を取る。
「やべえ」
「逃げろ」
革ジャン、リーゼントの連中は慌てて逃げだした。武田は痛みをこらえて腕を押さえている。腕からは鮮血がしたたり落ちていた。
命にかかわる事態は避けられたが、腕の腱が切れ武田はギターが弾けなくなった。
「武田さん、大丈夫なんでしょうか」
美佐子はマスターに聞いた。
「落ち込んでるらしいよ。大学にも行ってないらしい」
「武田さんのお住まい、わかります?」
「ああ」
マスターは武田のアパートの住所を記したメモを美佐子に渡す。メモを頼りにアパートを訪ねると、ぼさぼさの髪をかきながら武田は姿を見せた。
「大丈夫ですか? 心配になって」
「ああ……」
武田は美佐子の目を見ずに答える。
ドアの前に立つ美佐子は、部屋の中をのぞき見る。部屋はゴミが散乱し、洗濯物がうずたかく積み上げられている。
「お掃除、しましょうか?」
「え?」
「掃除くらいなら、わたしにだってできます。これまでのお礼」
「なんだよ、礼って」
「だって、ずっとジュース代、おごってくれてたじゃないですか」
美佐子は、できるだけ明るい表情を浮かべていった。それが、美佐子にできる精いっぱいの慰めでもある。
無理やり部屋のあがりこみ、美佐子は掃除をはじめる。洗濯物は一つにまとめ、押し入れに押し込んだ。
「洗濯機の場所がわからないから、申し訳ないけど自分でなんとかしてください」
敷きっぱなしだった布団もたたみ、部屋はずいぶんきれいになる。畳の上に美佐子は正座し、あぐらをかいてハイライトを吸う武田と向かい合った。
「マスター、心配してましたよ」
「ああ」
「少しは顔をお見せになったほうが」
「なにしに行くんだよ」
「だから……」
「ギターの弾けなくなったオレが、なにしにあの店に行くんだよ!」
憤りを含んだ声で武田はいい捨てる。
「ギターも弾けない、歌も歌えない、学校もやめた。もう終わりだよ」
「そんなこといわないでください。ギターが弾けなくても歌は……」
「お前にいったい、なにがわかるっていうんだよ!」
武田は美佐子をにらみつけた。
「お前にオレ気持ちがわかるか? わけのわかんないヤツに腕刺されてさ、その瞬間に夢が消えちまったんだぜ。歌を歌いたくて東京に出てきたのに、全部パーになっちまったんだぜ」
「でも、歌が歌えなくても……。その、じょうずにいえませんけど……」
「お前、なにしにこの部屋にきたんだ」
「え? その、心配で」
「慰めにきたのか?」
「は、はい、まあ……」
美佐子を見る武田の眼光が鋭く光る。獲物を捕らえる瞬間の獣のように。
「じゃあ、慰めてくれよ」
「え?」
「お前の身体で慰めてくれよ!」
武田は美佐子に覆いかぶさった。
「い、いや、やめて、やめて!」
「無茶苦茶になりてえんだ。無茶苦茶になりてぇんだよ。もう何もかも、何もかもがいやなんだよ!」
武田はワンピースの胸元を乱暴に開いた。素肌を覆うシミーズが見え、こんもりとした胸のふくらみがあらわとなる。
「やめて、やめてください」
「なんだよ。心配したとか、慰めるとか、結局口から出まかせか」
「そんなんじゃない。そんなんじゃない」
「じゃあ、身体で証明してくれ」
ワンピースをはがし、シミーズを脱がす。いままで男に肌をさらした経験のない美佐子は、羞恥と恐怖で身を震わせる。
武田はブラジャーの上から乳房をわしづかみにした。それだけで美佐子の意識は遠のいつつある。
これから自分はどうなってしまうのか。武田に好意はいだいていた。けれど、それは兄に対する思慕のようなものであり、恋愛ではないとも思っていた。
そもそも美佐子は、人を恋したことがない。これまで男性と知り合うきっかけは皆無に近かったし、最近でも意中の人と呼べる相手とは出会っていない。
だが、このときをきっかけに武田が恋愛の対象になってもいい。不満はない。しかし、順番がおかしい。
「いや、やっぱりいやです」
「四の五のいうんじゃねぇよ」
武田はブラジャーをずりさげ、美佐子の胸乳にしゃぶりついた。右手は下着の中に忍び込み、きつく閉じた美裂をさぐる。
「……」
伝わる感触に美佐子は言葉を発することができない。
大人の男女が結ばれる行為自体は、知識として持っている。だが、薄汚れたアパートの一室で、シャワーも浴びず、乱暴に辱められるものではないとの認識はある。
それが、今まさに行われようとしている。思考が混乱し、精神は現実から逃避してしまう。
武田は美佐子の下半身をむき出しにし、自分もズボンと下着を脱いで、性急にいきり立った一物をねじ込んだ。
「あ!」
脳髄まで到達するような勢いと、股間が裂けるような激痛に美佐子は耐える。全身がばらばらに弾けてしまいそうな感覚の中で、夢中になって腰を振る武田の動きを受け止めた。
終わったあと、武田は泣いた。
「すまない。ごめんな。ごめんなさい」
そんな武田の姿を見て、素肌にワンピースを押しつけただけの美佐子は憐れみをおぼえる。
「歌、歌ってください」
「え?」
「祭りのあと。歌ってください」
美佐子はぽつりとつぶやく。
「お願いします」
武田は拳で涙をぬぐった。
「伴奏なしでいい?」
「うん。歌が聞きたいだけだから」
武田は一つ咳ばらいをし、歌う。
「祭りの、あとのさびしさが、いやでも、やってくるのなら……」
武田は歌う。朗々と歌う。美佐子は、そんな武田を見つめながら聞き入る。
「日々を慰安が吹き荒れて、帰ってゆける場所がない、日々慰安を吹き抜けて、死んでしまうには早すぎる」
吸い殻になったタバコのにおいが美佐子の全身にまとわりつく。歌詞の意味をはっきりと把握できないにしろ、武田が歌うと心の琴線を震わせる。
「もう恨むまい、もう恨むのはよそう、今宵の酒に酔いしれて……」
「わたしも恨みません」
「え?」
「きょうのことは恨みません。だから、きちんと生きてください。約束してくれますか?」
武田は美佐子を見つめた。
「ああ」
「ありがとうございます」
笑みを浮かべる美佐子。武田は新しいタバコを取り出し、あの店のマッチで火を着けた。
それから武田と美佐子の関係は深まった。歌をあきらめた武田だが、日雇いの現場仕事で糊口をしのぎ、なんとか生活を成り立たせていた。しかし、社会の現実に触れることで、絶望感は増していく。そのうっぷんを、武田は美佐子の身体で晴らした。
武田に抱かれる回数が増えるにつれ、美佐子も女としての歓びを実感するようになる。
「いい、あん、気持ちいい」
「お前、淫乱だな」
「そう、でも、あなただけ。武田さんだけ」
「本当か?」
「ホント……、やん、すごい」
武田の肉棒を受け止め、内部をこすられる感覚に美佐子は歓喜をあらわにする。武田も美佐子の窮屈で温かで、ぬめりのある感触に溺れた。
美佐子の肌は白く、吸いつく触感をたたえている。乳房はさほど大きくもないが、形は整い、桜色した乳首の味は舌にとろけるほど甘露だ。
武田は美佐子を愛した。しかし、不器用な武田は、それをうまく表現することができずにいる。そして、美佐子を貫き、一つになれることだけでしか幸福感を得ることができない。
それでも美佐子は満足だった。たとえ自分が性欲を処理するだけの対象であっても、武田が束の間の幸せを感じてくれるのであれば、それでいい。自分の肉体が武田の役に立っている。そう考えるだけで充足感が得られる。
「やああん、いい、ステキ」
「いいのか、そんなにいいのか?」
「いい、やあああん、だめぇ、イッちゃう!」
武田はそのまま吐き出す。大量の精虫が美佐子の胎内を泳ぎ回る。危険だとは思う。思ってみてもあらがえない。わたしがいるから、この男は生きている。そんなふうにも思う。少しでも拒絶を示せば、その瞬間にこの男は命を絶つだろう。
「生きてね、絶対、生きてね」
「ああ」
射精のあと、武田はあお向けに寝転がりタバコの煙を吐く。紫の煙がたなびき、天井に上っていく様子を、美佐子はぼんやりと視線で追った。
そんな二人にも別れが訪れた。原因は武田の困窮だ。仕事を転々としていた武田は、肉体労働に嫌気をさす。かといって、ほかにできそうな仕事はない。生活費に事欠き、美佐子に無心もするようにもなる。
美佐子は自分の小づかいの中から工面し、足りないときは親にねだった。だが、それにも限度がある。そして、ある日、美佐子は父親から通告を受けた。
「美佐子、男の家に通っているらしいな」
「え?」
父親は興信所から示された書類を見せる。
「パパ……」
「こんな形で娘の素行を調査することになるとは、思いもよらなかった。母さんに聞くと、小づかい以外にお金をねだっているそうじゃないか。男に貢いでるのか?」
「それは……」
「男の素性も調べた。田舎から出てきた歌い手崩れらしいな。ろくな仕事もしていない。そんなヤツに娘を好き放題討させるわけにも、ましてや金を渡すこともまかりならん」
続いて父親は、写真を1枚示す。
「わしの懇意にしている会社の息子さんだ。次の日曜日に見合いをする。お前は、彼のところに嫁ぐんだ」
「そ、そんな……」
「口ごたえは許さない。その代わりといっちゃあなんだが、いまの男と別れるための金を用意してやろう。これもお母さんから聞いた。お前、結構な金額を用意してくれって頼んだそうだな」
武田は家賃を滞納し、すぐにでも立ち退くよう迫られていた。滞納は半年分におよぶ。しかもアパートは取り壊しになる予定で、次の住処を見つける資金も必要だ。
「わしが立て替えてやる。その代わり、いいな」
美佐子に逆らうすべはなかった。
武田に別れを告げた後、美佐子はしゃくりあげながら立ちあがり、部屋を出ていこうとする。武田は、そんな美佐子を見送ろうともしない。
ドアの取っ手に手を伸ばし、美佐子は振り返って武田を見た。武田は相変わらず、窓を見ながらタバコを吹かす。
「ねえ」
「ん?」
「ううん」
美佐子は外へ出た。
雨が降り続く。傘をさして美佐子は武田の部屋を見る。涙で風景がゆがむ。そのとき、ポケットの中にマッチが収まっているのに気づいた。
武田と初めて出会った店のマッチだった。
美佐子は1本取りだして火を着けた。そしてすぐに消す。白い煙が揺らぎ、思い出のよみがえる香りがひろがる。
マッチを水たまりに捨て、美佐子はしばらく見つめる。
「さよなら」
見つめながらつぶやき、美佐子は歩きはじめる。ふたたびあふれてきた涙をぬぐおうともせずに。
- 【長月猛夫プロフィール】
- 1988年官能小説誌への投稿でデビュー。1995年第1回ロリータ小説大賞(綜合図書主催)佳作。主な著作『ひとみ煌きの快感~美少女夢奇譚』(蒼竜社)/『病みたる性本能』(グリーンドア文庫)/『19歳に戻れない』(扶桑社・電子版)ほか。
この記事の画像
関連キーワード
 Linkage
関連記事
Linkage
関連記事
-

昭和官能エレジー第10回「アンパン中毒のフーテン少女」長月…
-

昭和官能エレジー第9回「ブルーフィルムの兄妹」長月猛夫
-

昭和官能エレジー第8回「淫乱女との同棲生活」長月猛夫
-

昭和官能エレジー第7回「不良少女との残念な初体験」長月猛夫
-

【昭和官能エレジー】第6回「雨とカラオケとスナックの女」長…
-

【昭和官能エレジー】第5回「一人暮らしの女」
-

昭和官能エレジー第4回「不良少女との約束」長月猛夫
-

昭和官能エレジー第3回「変わってしまった女との手痛い別れ」…
-

昭和官能エレジー第2回「未亡人との夢物語」長月猛夫
-

昭和官能エレジー「純情ホステスの純愛芝居」長月猛夫
-

あの週刊大衆が完全バックアップした全国の優良店を紹介するサイト
 FANZA新着動画
特選素人娘マル秘動画
FANZA新着動画
特選素人娘マル秘動画
-

【VR】めちゃくちゃオッパイが近い♪ 巨乳×座位 濃密30…
-

個撮ナンパ #ニットから飛び出るロケット爆乳美女#Kカップ…
-

PRIVATE~ヨーロピアン美少女たちのロマンチックな愛の…
-

PRIVATE~The Love Hotel セクシー美女…
-

「おばさんでいいの?」観念して若いチ〇ポを咥えだす!
-

上品淑女が四つん這い!理性吹っ飛び、おねだりしちゃう…。
-

旦那にはしない濃厚フェラ。経験人数少ないレアな人妻生保レデ…
-

素人福袋 ナンパされた美巨乳お姉さん150人 2400分 …
-

エロい期待でその気満々!! 下着グチョ濡れ敏感熟女