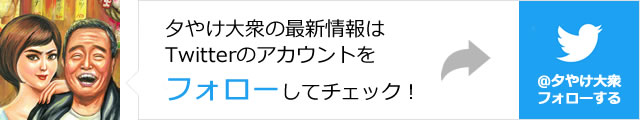Catch Up
キャッチアップ
Catch Up
キャッチアップ

この官能小説は、現在50代から60代の方々の若かりし時代を舞台背景にしています。貧しかったけれど希望に満ち溢れていたあの頃、そこには切なくも妖しい男と女の物語が今よりも数多く存在しました。人と人とが巡り合う一瞬の奇跡、そこから紡がれる摩訶不思議な性の世界をお楽しみください。 編集長
【アンパン中毒のフーテン少女】長月猛夫
せんべい布団の上であぐらをかき、下着だけをはいたナオミはタバコをふかしていた。
薄い胸に病的なほど白い肌。長く伸ばされた素直な髪は、腰からヒップのラインに沿って曲線を描いている。
その横では正座をした晃がうなだれている。
「ナオミ、もうやめてくれよ」
ひざの上に置いたこぶしを握り締め、晃は絞り出す声で訴えた。
「どうして?」
長い髪をかきあげ、ナオミはけだるい声でたずねる。
「どうしてって……」
「アンタはアタイのなんなの?」
「なにって……」
「親? 兄貴? 先生? だんな? それとも彼氏?」
彼氏という言葉に晃はピクリと反応を示すが、的確な答えは見いだせない。
夏の夕暮れ時、ひび割れた窓ガラスから西日が差し込んでいる。歓楽街の中にある、いまにも崩れ落ちそうなマンションの3階。周囲のネオンがまたたきはじめ、カラフルな明りがすりガラスに映る。
「あれ? ナオミ、先客?」
突然、部屋の扉が開き薄汚れた男が顔をのぞかせた。裾の広いパッチワークだらけのジーパンをはき、身に着けているものは身体に張りつくサイケデリック模様の開襟シャツ。髪の毛はナオミと同じほどの長さに伸ばされ、頭にはヘアバンド、顔には丸いサングラスをかけている。
「客じゃないよ」
「そうなんだ」
男は無遠慮に部屋の中ほどまで進み、ナオミのとなりに腰をおろす。
「いいブツを仕入れてきたんだ」
男は茶色い小瓶をナオミに手渡した。受け取ったナオミは栓を開けて鼻を近づけ、息を吸い込む。
「うん、いい感じ」
「上物のトルエンだ」
「ふ~ん、アリガト」
もう一度においを嗅ぎ、ナオミは栓をして布団の横におく。その様子を好色な目でながめたあとで、男は晃を一瞥する。
「お客さんだから出て行って」
ナオミは両脚を投げ出し、パンティを脱ぎながら晃にいった。
「ナオミ……」
「出て行って」
冷たく言い放たれる言葉に、晃は呆然と立ちあがる。晃を見あげた男は視線をナオミに戻し、にやけた表情でシャツのボタンをはずした。
60年代後半に吹き荒れた学生運動の嵐も、69年1月の東大安田講堂陥落によって徐々に沈静化する。敗北によって無気力化した若者たちの間には厭世的な空気が漂い、蔓延したのがヒッピー・ムーブメント。ただし、日本ではヒッピーを気取る若者を「フーテン」と呼び、彼らも自虐的に自称した。
ナオミも、そんなフーテン族の一人だった。
晃がナオミと出会ったのは、友人の西沢に誘われて入ったゴーゴー喫茶だ。
耳をつんざく轟音とまばゆいストロボ照明を浴び、男女が入り乱れて身をくねらせている。その様子に圧倒されながら、晃は西沢にうながされてソファー席につく。
「な、すごいだろう」
「え!?」
「すごいだろ!」
となりに座っていても、音がうるさくて西沢の声がよく聞き取れない。
「さすが東京って感じだろ!」
「え、なに!?」
西沢は音楽に合わせて身体を揺らす。そんな西沢を見て、ホールで踊っていた女性がウィンクをして目配せした。
西沢は破顔して立ちあがる。
「踊ってくるよ」
西沢はそう言い残して、目当ての女性に近づいていく。残された晃は所在なげに、そのままの場所で座っていた。
晃が生まれ育ったのは北関東の農村だ。実家は江戸時代まで庄屋を務めていた豪農の家系で、戦後に農地改革が行われても、それなりの土地と資産を有していた。
長男の晃は進学校に入学し、卒業すると東京の大学に進学した。上京する際、駅まで祖父母や両親、村長以下、村の住民までも見送りに来たのをおぼえている。
晃は、そんな期待に応えようと勉強に励んだ。ただ、彼が思い描いていた将来は詩人になることだった。
小学校のころ、授業の課題で生まれて初めて詩を書いた。それが教師に褒められ、しかも新聞の地方欄に投稿作品として掲載された。家族は喜び、近所の人からほめそやされ、天才だともてはやされた。
それから晃は詩人を夢見る。しかし、中学、高校と進学するうちに現実を見据え、詩では生活もままならず、しかも田舎ながらも名家の跡取りという立場に相応しくないと自覚。詩は趣味の範疇にとどめ、勉強の合間に詩集を読むことだけを楽しみとした。
大学生活の春が終わり、夏が訪れたとき晃は西沢と出会った。きっかけは晃が読んでいた詩集だった。
大学の構内で、晃はベンチに座って萩原朔太郎の『月に吠える』を開いていた。
「君は朔太郎が好きなんだね」
そう声をかけてきたのが西沢だった。
「はい」
人見知りの強い晃は、そう答えるのが精いっぱいだ。
「日本人の詩はおもしろいかい?」
「え?」
「僕はボードレールやヴェルネールといった、フランスのデカダンスが好きだな」
晃にとって初めて耳にする名前だ。
「君、名前は?」
「藤井です。藤井晃」
「何年生?」
「1年です」
「じゃあ同じだ。現役生?」
「はい」
「歳は僕のほうが一つ上だな。おっと、でも同じ学年だから敬語はなしにしようぜ。あ、申し遅れた。僕は西沢、西沢正則」
それから晃と西沢の付き合いははじまった。
西沢はフーテン族ではなかったが、東京の繁華街には詳しかった。そして、何かつけて晃を誘い出し、飲みに出かけては文学や思想、政治に関して議論を吹っ掛ける。ただ、晃が何をいっても、西沢はこういって否定する。
「ナンセンスだ、ナンセンス。君の言っていることは日和見だ」
それでも、それまで知らなかった新しい世界を垣間見せてくれる西沢に対し、晃は好感を持った。
そんな西沢は晃をゴーゴー喫茶に連れ込んだ。しかし、晃は一人取り残されてしまう。西沢の帰りを待ちながら、周囲を見回す晃。そして目が合ったのがナオミだった。
マキシスカートに長袖のTシャツを着たナオミは、少し離れたソファーで、うずもれるようにして座っていた。手にはナイロン袋を持ち、口に当てて呼吸をくり返している。中身がシンナーであることは、晃にもわかった。
髪の毛を七三にわけて度の強い眼鏡をかけ、襟のある無地のシャツを黒いスラックスに押し込んだ晃。そんな場違いの格好にナオミは興味を示したのか、よろよろと立ちあがると晃の横に座る。
「アンタ、なんでここにいるの?」
「え? なに?」
「なんでこんなところにいるのよ!」
叫ぶようにナオミは話す。
「なんでって言われても……」
「え?」
今度はナオミが聞き返した。
「聞こえないよ!」
ナオミは耳を晃の口元に近づける。女性を知らない晃は、それだけで緊張してしまう。
「……」
驚いた晃は口ごもってしまった。すると今度は、ナオミが晃の耳に口をつけて話す。
「アンタみたいな優男がさ、なんでこんなところにいるの」
息が耳たぶに吹きかかる。くすぐったく、それでいて甘美な感触に、晃は思わずナオミの顔を注視してしまった。
シンナーでラリッているナオミのまなざしは、とろんとして焦点が合っていない。唇は真紅のルージュが塗り込まれ、反り返ったまつ毛に覆われた目の周りは、ラメ模様に彩られている。
それでも晃は、どことなく幼さの残るナオミに可憐さを見出してしまった。
「あ、アンタの指、きれい」
ナオミはいきなり晃の手を取り、指をながめる。突然手に触れられた晃の緊張はピークに差しかかり、心臓が早鐘を打つように鼓動をくり返した。
「指のきれいな男は、アソコもいいんだよ」
「アソコ?」
「そう、チ×ポ」
「……!」
「ねえ」
「な、なに」
「出ようよ」
ナオミは晃の返事も待たず、手を握って立ちあがる。そして、そのまま店の外に向かおうとする。
「ちょ、ちょっと……」
晃は動揺をおぼえるが、逆らう意思は持たなかった。
ゴーゴー喫茶の入る雑居ビルの裏。錆びた螺旋階段の下で、晃は壁にもたれかかっていた。ナオミは晃の前にしゃがみ、ズボンから取り出した一物をしゃぶる。
「う、んん……。はあ……。予想通り大きいね。けど、硬くならない」
口からはずして手で乱暴にしごき、少し力がこもると舌を伸ばして舐りながらほおばる。しかし場所が場所だけに、緊張を禁じ得ない晃の男根は血液の充満を果たせずにいる。
「オッパイ揉めば、少しは大丈夫かな」
「え、いえ、そんな問題じゃ……」
「どんな問題?」
「だから、こんなところじゃ」
「ハンチクなこと言ってんじゃねえよ。女が自分から誘ってんだよ。男なら気合い入れて犯してみろよ」
上目づかいでナオミは罵声を浴びせる。かといって、気合いを入れたからといって簡単に勃起するものでもない。
「しょうがないなぁ」
ナオミは立ちあがってTシャツを脱いだ。ブラジャーはつけていない。ふくらみは手のひらに収まる程度でつつましやかだが、欲情をそそるにふさわしい形を整えている。
「ほら、揉んでみなよ」
晃の両手をナオミは胸乳に押しつける。手のひらの中央に乳首の感触が伝わる。指に力をこめれば、張りのある乳肉がやわらかくはじき返してくる。
晃はわしづかみにしたまま、手のひらを揺り動かした。
「うん、いい、指がいい」
ナオミの口から切ない声が漏れる。
「いいよ、吸っても」
晃はナオミの表情を確認し、顔を押しつけて乳首をふくむ。幼いときに舐めた金平糖に似た味わいがひろがる。舌の上で転がせば、コロリとした触感が艶めかしい。
「うん……、そう、そう」
ナオミは露出した肉棒を握ってしごいていた。興奮をおぼえた晃は、勃起を果たす。
「これで大丈夫だね」
ナオミは薄く笑うとスカートを腰までまくりあげ、下着をおろす。そして晃に背中を向けると、自分で内部に誘導した。
「あ、くん……」
膣筒をひろげられる感覚に、ナオミは眉根にしわを寄せ反応を示す。
「うん、いい感じ」
晃は覆いつくす粘膜の感触と、胎内の温度、そして愛蜜のぬめりを甘受した。
晃にとっては初めての体験だった。いつかは誰かと、こんな機会があるとは思っていたが、まさか出会ったばかりの女性と、しかも屋外で経験するとは予想だにしていなかった。
ただ、後悔はない。僥倖であるとすら思ってしまう。
西沢と出会い、そしていまナオミと肉欲を交わしている。超絶した世界観がひろがり、変わりつつある自分自身がおもしろくもある。
締めつける肉襞の感触に、晃は陶然となる。ナオミは蜜の多い体質なのか、あふれ出る雌汁で互いの下半身が濡れる。
晃はナオミの背中に覆いかぶさり、乳房に手を伸ばした。ふくらみは興奮に応じて、かすかにボリュームを増す。
「あん、あん、いい、いいよ、アンタ、いい。やああん、気持ちいい」
ナオミは周囲を気にせずに甲高い声をあげた。晃は夢中になって腰を打ちつけ、ナオミの膣内を攪拌する。肉壁に羅列する肉粒が蠕動して晃の包皮を刺激する。歓喜が昂るにつれて圧力が増し、肉柱の芯を絞る。
ナオミも肢体を伸縮させながら、晃に律動を加えた。自分と呼応する抽送の感覚に、晃は頂点が間近に迫るのを知る。
「出そうだよ、出る」
「出してよ、出して、そのままでいい」
「それはだめだよ」
「いいんだよ。やあん、気持ちいい、いいい!」
ナオミは激しい動きで臀部を打ちつけた。晃に抜き取る余裕はなく、そのまま熱いほとばしりを放つのだった。
「君さ、とんでもない女に引っかかったんだって」
西沢はいう。
「とんでもない女じゃない」
「どうして? アンパン中毒のパン助だろ。シンナーさえ渡したらだれとでも寝る女だろ」
「どうしてそれを」
「行きつけの店で聞いたんだよ。ナオミって女がさ、新しい男咥えこんでるって」
西沢の言うとおりだった。
ナオミとの官能的な体験を果たしたあと、晃はその身体と行為に溺れてしまった。そして、ナオミの住むマンションに通っては、肉体をむさぼる。
ナオミも晃を拒絶はしない。ただ、終わったあとにいくらかの金銭を無心する。晃の生活は、すべて親からの仕送りで賄っていた。とはいえ、実家は莫大な財産を持つ資産家だ。不足を訴えると、すぐに書留で送ってくる。それをそのまま、晃はナオミに渡す。
しかし、晃はシンナーやトルエンを調達する手段を知らない。用意するのはナオミの身体目当ての男たちだった。
「こんなことやめようよ。シンナーなんかやめてくれよ」
男が帰った部屋の中で、晃は懇願する。
「やだよ。アンパンなしじゃ生きていけない」
「生きるどころか、死んじゃうよ」
「いいよ。こんなクズみたいな世の中、こっちからオサラバだよ」
苦渋の日々が過ぎる。それでも晃はナオミから離れることができない。理由はわからない。セックスだけがナオミの魅力ではない。
では、なにか? なにがそれほどまでに自分を魅了するのか?
自分とはまったく違う世界観を持つナオミ。過去のことを決して話はしないが、晃の知ることのない経験を重ねてきたことだけはたしかだ。
それを知りたい。いや過去のことよりも、過去に培われたナオミという人間を知りたい。
そんな好奇心が晃を駆り立てる。
「アンタもやってみればいいんだよ、アンパン」
「それは」
「怖いんだ。あいかわらずの意気地なしだな」
ある夜、晃はナオミをマンションの屋上に誘った。部屋の蒸し暑さと、男たちの吐き出したザーメンのにおいを厭ったからだ。
「ちょっとはましだろ」
「そうだね。涼しい」
空には満月が浮かび、青い光が冷たく二人を照らす。時折ぬるい風が吹き、歓楽の嬌声を運んでくる。
「ココでする?」
ナオミはいう。
「アタイのとこにきたの、それが目的だろ」
「ああ」
ナオミはふわりと髪をかき上げてシャツを脱ぎ、つぎはぎだらけのジーパンをおろす。あいかわらずブラジャーはつけていない。
コンクリートの上に下半身を露出させた晃はあお向けに寝そべり、下着も落としたナオミはまたがった。
「くうん、う……」
子犬のような声を出し、ナオミは晃を迎え入れる。蜜壺の中は粘りのある襞がうごめき、晃を奥へ奥へと導く。
全裸のナオミが舞い踊る。純白でしなやかな肢体が月光に浮かびあがる。その姿は、現実世界を超越した神々しさに満ちている。
ナオミが身体を揺らすごとに、ピチュクチュという淫靡な摩擦音が響いた。ナオミは顎をあげ、背中をそらして光悦に浸る。
「すごいよ、すごい。アンタ、いい、一番いい」
「いいのか、僕が」
「うん、いい、すごくいい」
真実かどうかはわからない。けれど、その一言に安堵する。
髪を振り乱しながら、ナオミは上下する。とば口で晃を挟み込み、窮屈な刺激を与え続ける。
ナオミの最も奥深い部分まで貫きながら、晃は肉の圧迫を感じ取った。膣筒のなめらかな感触は、業物をとろけさせる湿潤に満ちている。
一部分だけでなく、全身が溶解しナオミと一体化してしまう錯覚におちいる。細胞の一つ一つが交わりあい、皮膚も、筋肉も、骨格も、神経も、そして思考も共有してしまう。
淫靡で甘美な享楽の渦の中で、晃はナオミに樹液の注入を果たすのだった。
終わったあと、屋上のフェンスにもたれ、一糸まとわぬナオミはビニール袋に口を当てていた。
「ほら、アンタも」
射精後の虚脱の中で、晃の意識はあやふやになっている。
ナオミにすすめられるまま、晃はシンナーの蒸気を吸い込んだ。とろりと甘い匂いが鼻に浸透し、同時に脳神経が震えはじめる。呼吸をくり返すごとに身体の感覚が失われ、多幸感が増してくる。
「どう?」
「うん」
「ふふふ」
「ん? ん、ははは」
「きゃははははは」
「はははははははは!」
見つめあい、意味もなく笑い声をあげる晃とナオミ。腹をかかえ、身をよじり、涙を流して笑い転げる。
「と、飛べるかな」
笑いながらナオミがいう。
「え、え、え?」
「空、飛べるかな。空、飛べたらさ、いやなこと全部忘れられるかな」
「いやなことって、なんだよ」
「全部、この世の中のこと全部。アタイ自身も」
「僕のことも」
「そう、アンタもいやだ。大嫌い」
ナオミは身を起こし、フェンスのすき間からビルの屋上のへりに立った。晃はそれを呆然と見つめる。
「危ないよ」
「平気」
ナオミは両手を翼のようにひろげた。そして直立したままで前のめりになり、身をひるがえす。
ナオミの身体は街の空気に吸い込まれていった。
「あ……」
晃はナオミのいなくなったへりを見つめた。いつまでも、いつまでも見つめていた。
- 【長月猛夫プロフィール】
- 1988年官能小説誌への投稿でデビュー。1995年第1回ロリータ小説大賞(綜合図書主催)佳作。主な著作『ひとみ煌きの快感~美少女夢奇譚』(蒼竜社)/『病みたる性本能』(グリーンドア文庫)/『19歳に戻れない』(扶桑社・電子版)ほか。
この記事の画像
関連キーワード
 Linkage
関連記事
Linkage
関連記事
 FANZA新着動画
特選素人娘マル秘動画
FANZA新着動画
特選素人娘マル秘動画
-

【VR】心地よい囁きで脳イキが止まらない… 不眠症のボクに…
-

子宮直撃!!ガンガン突かれてピクピク痙攣奥まで中出しベスト
-

母さんとしてくれる?禁断のSEXを選んだ母、背徳感が母と子…
-

誘惑するのはまさかのドスケベお姉さん
-

大人のAVベストセレクション vol.24 平成の女教師ド…
-

新・大人のAV 官能ドラマ傑作選vol.27 9作品本編ま…
-

エグい程イキ狂うおばさんの不倫SEX
-

突然の大雨でズブ濡れになった濡れ髪と透け下着で無自覚にデカ…
-

シロウト人妻ナンパ中出し 奥さん、これからショートタイム不…