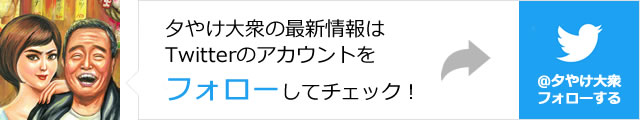Catch Up
キャッチアップ
Catch Up
キャッチアップ

昭和官能エレジー「純情ホステスの純愛芝居」長月猛夫
この官能小説は、現在50代から60代の方々の若かりし時代を舞台背景にしています。貧しかったけれど希望に満ち溢れていたあの頃、そこには切なくも妖しい男と女の物語が今よりも数多く存在しました。人と人とが巡り合う一瞬の奇跡、そこから紡がれる摩訶不思議な性の世界をお楽しみください。 編集長
【純情ホステスの純愛芝居】
戦争が終わって20余年。日本は高度経済成長期の真っ最中で、藤井は建材メーカーに勤めていた。
東京オリンピックは終わったものの、次には大阪で万国博覧会が予定されている。東京周辺のインフラはほぼ整えられたが、地方に目を向けると、開発の余地はごまんとある。
そんな時代だった。
ある日、藤井は中堅ゼネコン専務の接待に駆り出された。大学を出て2年、24歳の春だった。
営業部長と先輩、藤井の3人で専務をもてなす。気を使いながら酒を注ぎ、世辞をいいながら寿司を食べる。相手の顔色をうかがいつつ、おもしろくもない話題に笑い声をあげる。
接待の席は初めてではない。営業マンとして働く限り、接待が必要なのはわかっている。だが、どうしても馴染むことが出来ない。ヘラヘラとした笑みを浮かべている部長や先輩をながめながら、藤井は苦痛に思える時間を過ごした。
寿司屋を出て、4人はキャバレーへくり出した。専務のご指定である。
「ラウンジやクラブの女より、キャバレーのホステスの方がスレていないんだよ」
何をもってそう言い切れるのか、藤井にはわからない。そもそも、ラウンジ、クラブに随伴したことはあっても、キャバレーに出向くのは初めてのことだった。
歓楽街の真ん中に位置し、きらびやかなネオンをまたたかせ、黒いスーツに蝶ネクタイを締めた初老の男が客を出迎えるキャバレー。雑居ビルのワンフロアーではなく、ビル全体がひとつの店として営業していて、藤井は夜空に浮かぶ巨大な建物を見て、思わず見あげてしまった。
中に入ると広いホールで生演奏のバンドが楽器を奏でていて、薄暗い店内に派手な衣裳のホステスがうろちょろしている。ボーイに案内されて席に着くと、すぐにホステスが4人の間に座った。
ベテランらしい中年女二人と若い女が二人。藤井のとなりに腰をおろしたのがアケミだった。
胸元の大きく開いたスパンコールの煌めく衣裳を身につけていたアケミではあったが、その容貌には幼さが残っている。派手な化粧をほどこしてはいるものの、似合っているとはいえない。どちらかといえば、セーラー服を着せて素顔のままでいたほうが、しっくりとくる雰囲気だった。
瓶ビールを抜いて乾杯を終え、専務を中心にして話を弾ませていたが、アケミは笑みを浮かべるだけで会話の中に入ってこようとはしない。
「アケミちゃんはね、まだ、このお仕事になれていないの。だから許してあげてね」
そんなアケミの様子を見て、ベテランホステスは告げた。
「アケミは、いくつなんだ?」
専務がたずねる。
「18です」
小さな声でアケミは答える。
「じゃあ、酒は飲めないな」
「い、いいえ、大丈夫です」
アケミはあわてて、目の前にあったグラスのビールを飲み干す。その途端、勢いあまって咳き込んでしまう。藤井を除く3人は、その様子を見て笑い声をあげるが、ホステスたちは渋い表情をあらわにした。
「ごめんなさいね。ほかの子に替わってもらおうかしら」
ベテランがいった。だが、藤井ははっきりとした声で拒絶を示した。
「い、いいえ! いいんです、このままで」
全員が呆気にとられる。が、すぐに爆笑が起こる。自分の言葉に恥じて、うつむいてしまう藤井。
藤井はホステスという仕事をしながらも、純朴なアケミを気に入ってしまったのだ。もちろん、可憐な面立ちやドレスからかいま見える白い肌、胸もとを盛りあげる豊満な乳房も、その理由だ。
アケミは藤井の様子をチラチラうかがいながら、かすかに頬を赤く染めていた。
閉店の時間がきて、接待はお開きとなる。「蛍の光」の光が流れる店内で、藤井たちは席を立った。
そのとき、だれかが藤井の背広の裾を引っ張った。不審に思って振り返ると、うつむき加減の小柄なアケミが上目づかいで藤井を見ている。
「また、来てくれる?」
「え?」
「また、アケミに会いに来てくれる?」
専務と部長たちは出口に向かっている。藤井もあわてて、あとを追おうとする。けれど、アケミは放さない。
「うん、来る。絶対に」
「ホント?」
「本当」
その言葉にアケミは満面の笑みを浮かべ、ようやく背広から手を放した。
数日後、アケミのことが忘れられない藤井は、給料が出たこともあり、ひとりでキャバレーを訪ねた。席に通されて指名を聞かれ、藤井はうわずった声でアケミの名を告げる。
アケミは、相変わらず似合わないドレスと化粧で姿をあらわした。
「きてくれたんだ」
つぶらなひとみを細めてほほ笑み、アケミは藤井のとなりに座る。
「うん、約束だから」
「うれしい」
アケミはぎこちない態度でビールを注ぐ。
「アケミちゃんは?」
「いただいていいの?」
「いいけど、大丈夫?」
「大丈夫よ。もう焦らない」
いたずらな笑みを浮かべてアケミはいい、ボーイに頼んでグラスを追加してもらう。藤井は瓶を持ってアケミに注ごうとする。両手でグラスを掲げたアケミは、泡立つビールを見て楽しそうに口を開いた。
「じゃあ、かんぱ~い」
緊張で喉の渇いていた藤井は一気に飲み干した。アケミはチビチビと縁を舐めていた。
アケミの声は、舌足らずで甘い。そんな声色で、藤井にあれこれたずねてくる。
「そうだ、お名前聞いてなかった」
「藤井」
「藤井さん?」
「そう」
「ならフーさん。フーさんはお仕事、何してるんですか?」
「フツーのサラリーマン」
「フツーのサラリーマンって、どんなお仕事?」
「建材屋の営業だよ」
「営業? 営業って何するお仕事なんですか?」
藤井は返答に困る。モノをつくるわけではない。事務をするわけでもない。販売といえなくもないが、直接何かを売るわけでもない。
得意先を訪ねて世間話をし、頭をさげて注文を聞き、契約を結ぶ。時には、相手の機嫌をうかがいながら、酒を飲んで食事もする。それを18歳のホステスに、どう説明していいのかわからない。
「そうだな。得意先から契約をもらう仕事かな」
「ふうん」
アケミはあまり理解できていないようだった。
「ところでさ」
今度は藤井がアケミにたずねる。
「どうして、こんな仕事してるの?」
「アパートの大家さんに紹介されて」
「昼間は何してるの?」
「むかしは工場で働いてたけど辞めちゃった」
「どうして?」
そのとき、アケミの顔に影が落ちた。
「ゴメン……、悪いこと聞いたかな」
「ううん、大丈夫」
アケミはすぐに、もとの表情に戻った。
しばらく他愛のない会話を楽しみ、藤井は店を出ることにした。
「もう帰るの?」
アケミは不満げな表情を浮かべる。
「うん、あしたもはやいから」
「そうなの……。じゃあ、今度はいつ来てくれる?」
「そうだなぁ、ちょっと、わからない」
「わからないんだ?」
さびしそうな顔で、藤井を見つめるアケミ。その表情に心のざわつきと、胸の締めつけをおぼえた藤井は、かたくなな口調で告げる。
「きっと来る。必ず来るから」
「ホント」
「ああ、絶対に」
「じゃあ」
アケミは右手の小指を立てる。
「約束して」
小首をかしげて、藤井に手を差し出すアケミ。藤井は、おそるおそる自分の小指を絡める。
「ゆ~びきりげんまん、う~そついたら、ハ~リ千本、のーます」
にこやかにほほ笑むアケミ。藤井は身体の芯が熱く火照るのを感じ取りながら、アケミの指の感触を確かめていた。
何度かかよううちに、アケミは外で会ってほしいと頼んでくるようになった。
店で会う限り、お客とホステスの関係でしかない。もっと別の関係で仲良くしたい。それに、藤井の懐具合も心配だ。
「もっと別の関係?」
「そう」
「どんな関係?」
「やだ、女の子の口から言わせないで」
はにかむアケミの様子を見て、藤井の胸の内は穏やかでなくなる。
店が休みの日曜日、藤井はアケミが指定した駅で待ち合わせた。あらわれたのは、赤いセーターに膝下丈のスカートをはいたアケミだった。
化粧は薄く、年齢よりずいぶん若く見える。藤井はつい、ジロジロ見つめてしまう。
「おかしいかなぁ」
心配そうな顔つきでアケミはいう。
「ううん、ずいぶん印象が違うから」
「夜のアケミと昼間のアケミ、どっちがいい?」
「いまのほうが断然いい」
アケミは満面の笑みを浮かべ、藤井の腕にぶらさがってきた。
そのまま動物園へ行き、映画に入り、日が暮れると食事をとった。アケミは始終、楽しそうな笑顔を浮かべている。
「今度はいつ会おうか」
帰り道、藤井はアケミを駅まで送りながらたずねた。
「え、もう終わりなの?」
すねたような表情でアケミはいう。
「だって、時間が……」
「アケミ、もう少しいっしょにいたいなぁ。そうだ、ウチに来ない」
酒も飲まないのに、アケミのひとみはかすかに潤んでいる。藤井は驚きで、言葉がうまくつむげない。
「アケミ、もっといっしょにいたい。フーさんのこと、もっと知りたい」
少女のようだったアケミの面立ちが、女のものに変化しはじめる。
藤井は童貞ではなかったが、女性と深く付き合ったことがなかった。それでも、アケミの言葉が何を意味するものか察してしまう。
接待でたずねた店でアケミを知り、ひと目で気に入ってしまう。そして、アケミには玄人とは思えない素朴さが備わっている。何度か会っているうちに、アケミの可憐さや素直な性格に、ますます惹かれる。専務の言った、キャバレーのホステスの方がスレていないというのは、こういう意味なのかと推測する。
藤井は、アケミと出会ってから今までを思い返していた。
「どうする?」
背中に手をまわし、少し前かがみになって藤井の顔をのぞきこみながら、アケミは不安そうな顔できいてきた。
「いいの?」
「うん」
「じゃあ」
アケミは藤井にしがみついてくる。やわらかなアケミの感触を受け止めつつ、藤井は胃の辺りからみぞおちにかけて湧きあがる、緊張と不安を知った。
アケミのアパートは、駅のすぐそばにあった。簡単な台所とトイレはあるが風呂はない。簡素な6畳1間には、女の子らしいぬいぐるみや人形が飾られていた。
藤井は部屋の中央でかしこまっていた。アケミは湯をわかして茶を入れ、小さなテーブルの上に差し出す。
「誤解しないでね。この部屋に男の人を入れるのは初めてだから」
アケミは藤井のとなりに腰をおろした。藤井はまともにアケミの顔を見られずにいる。
「ねえ、フーさん」
「なに?」
「アケミのこと、好き?」
藤井はアケミの顔を見つめ、首を縦に振る。
「どこが?」
「かわいいとこ」
「それだけ?」
「いままで、出会ったことのタイプ」
「なに、それ?」
「学校とか、会社とかに、アケミちゃんみたいな女の子はいなかった。どこが違うのかって聞かれると困るけど……。で」
「で?」
「もっと、アケミちゃんのことが知りたくなる」
「アケミのなにを?」
「いろんなこと」
言葉が途切れる。アケミはじっと藤井を見つめる。
空気が色づきはじめる。アケミの目もとに妖しさが漂う。長いまつ毛がかすかに震え、肉厚のある唇に艶が走る。
アケミはひとみを閉じて唇を突きだしてきた。藤井は顔を寄せて、そっと重ねる。次の瞬間、アケミは藤井に抱きついてきた。二人は互いに身体を絡ませながら、畳の上に転がった。
「さびしいの、なぐさめて」
唇を離したアケミはつぶやいた。
藤井はアケミのセーターをまくりあげる。そして、スカートをおろし、シミーズを脱がせ、下着姿にする。アケミは固く目を閉じ、あらがいを見せない。ブラジャーとパンティだけを残したアケミをあお向けに寝かせ、藤井はその肌を舐めはじめた。
「やあん、くすぐったい」
身をよじって、アケミはくすくす笑う。藤井はアケミの背中に手をまわし、ブラジャーをはずす。あらわれたのは、こんもりと盛りあがった白い乳房。すでにとがった乳首は、桜色に染まっていた。
「電気、消して」
うっすらと目を開けたアケミはいう。藤井は蛍光灯にぶら下がるひもを引っ張る。
闇の中でも、アケミの白い素肌はぼんやりと浮かんで見えた。白磁のような肢体は自ら発光し、神々しいまでの曲線を誇示する。
藤井は胸乳をむさぼり、パンティの中に手を忍ばせる。アケミの部分はじゅんわりと潤っていて、簡単に指が埋没する。
乳首を舐め、乳肉を揉みながら陰部をまさぐる藤井。アケミは声をかみ殺しながら身悶えし、切ない息を吐く。
藤井は興奮をおさえきれず、最後の1枚をはぎ取ると、身体をアケミの脚の間に割り入れる。そして、屹立した肉棒の先を裂け目にあてがい、グイと腰を入れた。
その日から、アケミと藤井は、いっそう懇意になった。普段は少女のようなアケミだが、身体を重ねるときは、人が変わったように淫靡になる。藤井の一物を口にふくみ、馬乗りになって腰を振ることもあった。
何度か会っているうちに、アケミは自分の過去を話すようになった。
中学を卒業すると、すぐに田舎から出てきて一人暮らしをはじめた。工場に勤めていたが会社は倒産。それでも親から仕送りの催促がきた。しかも、父親が病気を患ったとかで、金額は増えるいっぽうだ。とうとう家賃が払えなくなり、キャバレーのホステスとして働くようになる。
「それでも大変なの」
「いくらいるの。少しならボクが」
「ダメ、そんなこと」
藤井は、真剣にアケミのことを愛していた。結婚してもいいとさえ思っていた。キャバレーを辞めさせ、自分の収入で養っていこうと考えていた。
「だから」
そのことを告げると、アケミは涙を流してよろこんだ。
「ありがとう」
その月から、藤井は毎月、ある程度のカネをアケミにわたした。アケミは感謝のつもりなのだろうか、藤井の身体を隅々まで舐めつくし、愛撫をあたえる。
アケミの愛らしさはもちろん、吸いつく肌と、豊満でやわらかい乳房、蜜壷のなめらかさから、藤井は逃れられなくなっていた。
そんなとき、父親がとうとう危ないといい、アケミは田舎に帰った。
「向こうでお父さんやお母さんにも話すから。落ち着いたら、次はアケミと一緒に実家に行ってね」
それが最後の言葉だった。
いつまでたってもアケミは戻ってこず、アパートも、もぬけの殻になっていた。
「オレ、だまされたのかなぁ」
アケミのことは信じたい。きっと、いつかは自分のところに戻ってきてくれる。
季節は秋の終わりに達していた。藤井はアケミとのこれまでを思い返し、しのびよる寒さに耐えた。
【長月猛夫プロフィール】
1988年官能小説誌への投稿でデビュー。1995年第1回ロリータ小説大賞(綜合図書主催)佳作。主な著作『ひとみ煌きの快感~美少女夢奇譚』(蒼竜社)/『病みたる性本能』(グリーンドア文庫)/『19歳に戻れない』(扶桑社・電子版)ほか。
この記事の画像
関連キーワード
 Linkage
関連記事
Linkage
関連記事
-

シニアのための夜の会話術 第11回「会話がダメなら身振りで…
-

【ネオン街ニュース】居酒屋「朝5時からの営業」で東京都全域…
-

【ネオン街ニュース】コロナでも風俗業界が休業できなかった本…
-

シニアのための夜の会話術 第10回「本当はエロいことわざ遊…
-

シニアのための夜の会話術 第9回「最後には食う男が勝つ」
-

シニアのための夜の会話術 第8回「中高年が新人に言いたいあ…
-

シニアのための夜の会話術 第7回「中高年は「笑納」を多用せ…
-

シニアのための夜の会話術 第6回 どんな猥談も紳士的になる…
-

シニアのための夜の会話術 第5回 女性がトキメク「お助けし…
-

シニアのための夜の会話術 第4回 褒めながら自分の意見を言…
-

あの週刊大衆が完全バックアップした全国の優良店を紹介するサイト
 FANZA新着動画
特選素人娘マル秘動画
FANZA新着動画
特選素人娘マル秘動画
-

個撮ナンパ #清楚で初心だと思ったら男好きな隠れビッチ女子…
-

いつでもドコでも即フェラ密着パイズリ4hours
-

毎日違うおっぱいに責められたい… 日替わり巨乳痴女SEXカ…
-

月野江すい プレミアムステージ初BEST8時間
-

「柔らか谷間に何度も出しなさい!」 射精直前の超快感パイズ…
-

奇跡の乳を持つ最胸シロウト 清原みゆう S1デビュー 1周…
-

男なら一度は抱きたい!高級ラウンジ嬢の超イイ女達とハメまく…
-

人妻自宅サロンBEST 底辺クズ隣人の汚らわしいデカマラに…
-

世界クラスのグラマラスボディ 気品溢れ出る本物CA 武田怜…