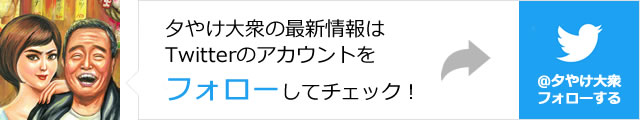Catch Up
キャッチアップ
Catch Up
キャッチアップ

この官能小説は、現在50代から60代の方々の若かりし時代を舞台背景にしています。貧しかったけれど希望に満ち溢れていたあの頃、そこには切なくも妖しい男と女の物語が今よりも数多く存在しました。人と人とが巡り合う一瞬の奇跡、そこから紡がれる摩訶不思議な性の世界をお楽しみください。 編集長
【となりに住むホステスとの甘美な関係】
10センチ四方の箱からマッチを取り出し、石油ストーブに火を着ける。ボッという音とともに炎があがり、灯油のにおいが部屋中にひろがる。
日曜日の午後、大森はコタツに入って寝転がり、テレビを観ていた。ストーブをつけ終えた妻の久子は、そんな大森を尻目にして台所の流しに立ち、昼食後の洗い物をはじめる。
部屋の隅では、5歳の息子が積み木を組み立てて遊んでいた。大森は上半身をあげてコタツの上に置かれたタバコに手を伸ばし、口に咥える。
視線はテレビに向けたまま。近所の喫茶店の名前がデザインされたマッチを探り、中から1本を取り出すと、箱の横の焦げ茶色の部分にこすりつけて点火する。
表情をしかめてタバコの先に火をかざす。息を吸い込んで着火を確認し、軸を持ったままマッチを上下に振る。役目を終えたマッチは、硫黄のにおいを漂わせ、白い煙がたなびく。それを無造作に灰皿に捨てた大森は紫煙を吐き、頬杖をついてふたたび寝転がった。
――ピンポーン。
そのとき、呼び鈴が鳴った。久子は洗い物を中断し、前かけで手をふきながら玄関に赴く。
「こんにちは。わたし、今度となりに越してきた……」
郊外にある団地の3階に、大森は妻と子どもの3人で暮らしている。となりは3か月前から空き室で、次の入居者が決まったようだ。
大森は、それとなく二人の会話に耳をかたむけた。
「これ、つまらないものですけど」
「まあまあ、ごていねいに。あら、ボクもお母さんとごあいさつまわり? 偉いわね」
「待っとけっていたんですけどね、いっしょに行くってきかなくて」
「おいくつ?」
「3歳です。やんちゃなもので、ご迷惑をおかけするかもしれませんけど」
「うちの子も5歳ですから同じようなものですわ」
やがてドアが閉められ、久子は台所に戻る。扉が開け放たれたときに吹き込んできた冷気が、ストーブの熱で温度をあげた。
「だれだ?」
テレビから目を離さずに大森はたずねた。
「引っ越しのごあいさつ。母親と子どもの二人暮らしみたい」
「ふ~ん」
「なんだか水商売っぽい雰囲気の人。年も若そうだし、気をつけなきゃ」
何に気をつける必要があるのか。大森は思う。
久子は見た目で人を判断する癖がある。さらに悋気持ちの性格でもある。ただ、それは恋愛感情からくるものではなく、独占欲と安定依存のあらわれだ。遊びもしないオモチャを捨てようとすると、幼児が猛反発するのに似ている。
久子は大森より2つ年下の33歳。いっしょになって7年がたつ。主婦として一日中、団地の一室にいるためか、普段は化粧をすることもなく、着るものにも気を使わない。
週に一度程度、身体を合わせることがあっても、それはたまった性欲の解消手段でしかなかった。心地よさはあっても感動はともなわない。久子のほうも義務的に応じるだけであり、出会ったころのような感動はない。
「水商売風の若い女、か……」
「え? なにかいった?」
「いや」
立春が過ぎたとはいえ、外の空気は鋭利な沈黙を吹き散らかしている。大森は窓にかかった薄いカーテン越しに、ちらりと外をながめ、短くなったタバコを灰皿でもみ消した。
1週間がたった。手持ちぶさたな午後に、大森はパチンコにでも行こうと部屋を出た。それと同時に、となりの部屋のドアも開く。姿をあらわしたのは、あいさつに来た女、尚子だった。
「あ、こんにちは」
尚子は明るい表情でいう。
「こんにちは」
大森は、若干の緊張をおぼえながら返す。
「はじめまして。おとなりのご主人?」
「ええ、まあ」
「越してきた……」
尚子は名前を告げ、大森も名乗った。
「これからお出かけですか?」
「ええ、はい」
大森は話しながら、尚子を確認した。
長い髪を一つに束ね、地味なジャンバーにジーパン姿。化粧は素顔に近く、久子のいう水商売っぽい雰囲気はうかがえない。ただ、背丈は低く細身の体格だが、胸のふくらみは大きく、上着の上からでも、そのボリュームが見て取れる。
「かあちゃん」
そのとき、閉まったドアの向こうから声が聞こえた。尚子があわてて扉を開くと、小さな子どもが出てきた。
「たっくん、おじちゃんにごあいさつなさい」
「こんにちは」
うながされた子どもは、たどたどしい声でいい、ぺこりと頭をさげる。
「これからどちらへ?」
いくぶん緊張のほぐれた大森はたずねる。
「買い物にでも行こうかと」
尚子は答える。
「じゃあ、そこまでごいっしょに。商店街まで案内しますよ。越してきたばかりで不案内でしょうから」
「いいんですか。ありがとうございます」
尚子は躊躇することもなく、素直な笑みを返した。
通路を歩き、階段を降りる。その間、大森は尚子の顔立ちを改める。
少し目尻のあがった大きなひとみと、肉厚のある小さな唇。口元のホクロが印象的だ。小柄ではっきりとした顔立ちなので、どことなく幼い愛らしさもうかがえる。それでいながら、表情やしぐさ、少しかすれた声は色香をかもしていた。
「なるほど」
久子は尚子の外見だけでなく、内に秘めた女の部分を一目で見抜いたのだろう。同性に対する的確な洞察力は、男に備わっていない能力だ。
「大森さんは、お仕事はなにを」
商店街へ向かう道すがら、会話の中で尚子はたずねた。
「普通のサラリーマンです」
「そうなんですか」
「お仕事は?」
「わたし? わたしは……。そうだ」
尚子はジーパンのポケットに手を入れ、マッチを一つ取り出した。
「わたしの働いている店のマッチです」
マッチにはスナックの文字と店名がデザインされている。久子の予想は的中した。
「大森さん、お酒は飲まれます?」
「ええ」
「じゃあ、よければ遊びにきてくださいね」
「え? いいんですか」
「もちろん。ちっちゃなお店ですけど」
「いえいえ、ぜひ」
「おとなりさんだもん。お安くしますよ」
尚子は相変わらずの笑みを浮かべる。ただ、尚子が夜の仕事をしていると知った大森は、夜の蝶に相応しい妖しさをイメージしてしまう。
仕事のときはきちんと化粧もし、髪形も整え、派手な衣装を身に着けるはずだ。いまの時点でも十分な麗しさを放っているのに、仕事のときはどんなふうに変わってしまうのか。
大森の期待はふくらむ。
やがて商店街に到着すると、入口のところで大森は尚子と別れた。
「ありがとうございました。助かりました」
「いえいえ」
「じゃあ、ここで。お店、きてくださいね」
尚子は頭をさげ、手を振りながら去っていく。その横で、手をつないだ子どもも小さく手を振っていた。
「おとなりさん、やっぱりスナックのホステスらしいわね。近くに実家があって、夜だけ子どもを預けてるらしいわよ」
数日後、夕食のあとに久子はいった。
尚子の年齢は26歳。結婚経験はない。つまり、子どもは私生児だ。
「お前、よくそこまで調べたな」
夕刊をひろげていた大森は、後片づけをする久子にいった。
「あら、こんなの簡単よ。あれこれ調べてくれる奥さんがいるから」
同じ団地に住む主婦連中が、顔を合わせると開かれる井戸端会議。他愛のない立ち話の中で、情報は交換される。
「仕事に行く前の格好を見た奥さんによるとね、派手な化粧に派手なドレス姿。靴はエナメルのハイヒールで……」
「もういい!」
大森は思わず声を荒らげてしまった。
「そんなうわさ話なんか聞きたくもない。女手一つで子どもを育てるために働いてるんだ。立派なもんじゃないか」
「あら、肩を持つのね」
「そんなんじゃない!」
大森の剣幕に、オモチャで遊んでいた子どもが泣き出した。あわててなだめる久子。
「出かけてくる」
いたたまれなくなった大森は、いつも着ているジャンバーをはおって夜の街に出た。
寒さはやわらぎを見せないものの、どこからともなく沈丁花の香りが漂ってくる。満月が青白い光で風景の陰影を際立たせ、敷地内に植えられた梅の木が小さく花を咲かせている。
部屋を飛び出てはみたものの、大森に行くあてはなかった。パチンコでもしようかと考え、ジャンバーのポケットからタバコを取り出す。
「マッチは……」
あちこちのポケットを探ってみると、胸の内ポケットの中にマッチがあった。1本を取り出してタバコに火を着け、大きく息を吸い込んでから煙を吐く。
空気が澄んでいるせいか、オリオン座の三つ星がよく見える。街灯の明かりを受けながら、紫煙はたなびいて消えていく。
大森は何気なく、取り出したマッチ箱をながめた。
「これは」
尚子から受け取ったものだった。
尚子は今日も店に立っているはずだ。派手な化粧に派手なドレス。足元はエナメルのハイヒール。久子の言葉が耳の奥でこだまする。
「よし」
行先は決まった。大森はマッチに書かれている店の所在地に向け、歩を進めた。
「いらっ……、あら、大森さん」
住宅街と繁華街の中間に位置する小さなスナック。ドアを開けると、尚子は驚いたようすで出迎えた。
「きてくれたんだ」
満面の笑みを浮かべる尚子。
10人がけのカウンターに、4人がけのボックス席が一つ。客の姿はない。カウンターの中には尚子だけだった。
大森はカウンターの中ほどに座り、尚子はおしぼりを手渡す。
「ボトルキープ制なんですけど、なにになさいます?」
「じゃあ、ダルマを」
尚子はサントリーオールドの黒いボトルを取り出し、大森の前に置く。
「水割りでいい?」
「うん」
キュッと音を立てて栓が開き、カチ割氷の詰まったタンブラーにトクトクとウイスキーがそそがれた。
「はい、名前書いてください」
マジックが手渡され、大森は自分の名をラベルに記す。
「ずいぶん待たされた」
尚子は、すねたそぶりでいった。
「もっと早くこようと思ってたんだけど」
「でも、きてくれてうれしい」
「お店、尚子さんが一人だけ?」
「きょうはママがお休みなの。ねえ、わたしもいただいていい?」
「どうぞ、どうぞ」
尚子は自分の水割りをつくる。
「いただきます」
グラスが触れ合い、かすかにチンと音がする。のどの渇きを覚えていた大森は、一気に飲み干した。
尚子は、髪を結いあげ眉を書き、アイシャドーを塗って真紅の口紅を引いている。それでも下品な印象は受けない。ラメの入ったドレスの胸元は大きく開き、乳房の谷間がはっきりとうかがえ、金色のネックレスがはさまっていた。
2時間ほど二人だけで過ごし、新しい客がきたところで大森は店を出る。
「きょうは楽しかった。またきてくださいね」
見送りに出た尚子はいう。
「もちろん」
大森は何度も振り返って尚子の姿を確認する。尚子は大森の姿が見えなくなるまで、手を振り続けていた。
その日から、大森は尚子の店にかよいはじめるようになる。カウンターをはさんで他愛のない話をし、カラオケにも興じた。ママがいるときは3人で話の花を咲かせ、ときにはほかの客と談笑を交わすこともあった。
そんなある日の夜。尚子の店の周年記念に、大森は招待される。尚子はあまり飲めない体質だが、記念日ということもあって、すすめられるままに何杯もグラスを空にする。やがて閉店間際になると、尚子は泥酔してしまった。
「大森さん、尚子ちゃんと同じ団地でしょ。送っていってあげてよ」
まともに立っていることもできない尚子を見て、店のママはいう。
「え、別にいいけど」
「タクシー呼ぶわね」
歩いて帰れない距離ではないが、尚子の状態を見るとしかたがない。
団地についてタクシーを降り、大森は尚子をかかえて部屋へ連れていく。
尚子のやわらかな感触が身体中に伝わる。腕が大森に絡みつき、乳房がひじや脇に押し当てられる。
香水の甘い香りが鼻腔の神経を震わせ、なにかをつぶやく甘い声が鼓膜を揺るがす。艶然とした表情に、ブラジャーの端が見えるほどひろがったドレスの胸元。
大森は興奮のたかぶりをおぼえつつ、階段をのぼって尚子の部屋にたどり着いた。
尚子からカギを受け取り、部屋の中へ。間取りは自分の部屋と同じだから、照明のスイッチの場所もわかっている。
居間に入って灯りをつけ、大森はとりあえず畳の上に尚子を横にした。
「水、お水……」
尚子はうわごとのようにいう。大森は台所の水道の栓をひねり、グラスについで尚子に渡す。
身体を起こして一気に飲み干した尚子だが、そのあとすぐに寝転んでしまう。
ドレスの裾が乱れて、肉づきのいい太ももがあらわになっている。呼吸は荒く、隆起した胸元が大きく上下する。
大森は、そのようすをじっと見つめていた。
かかえた尚子の肉の感触で、ボルテージは十分あがっている。まだ勃起にはいたっていないものの、股間の一物はうずうずと充血しはじめている。
このまま襲いかかってやろうか、とも思う。だが、それをしてしまうと、これから店に行くことも、顔を合わせることすらできなくなる。
いや、これだけ酔っているのだから、なにがあっても記憶には残らないはずだ。昏睡する尚子を堪能し、証拠を残さなければ大丈夫。
そんな考えも頭をよぎる。
「う、う~ん、あ……」
そのとき、尚子が目をさました。
「ここは? たっくんは?」
尚子は自分のことよりも、まずは子どもの心配をする。
「ママが実家に連絡してくれたから」
「え? あ、大森さん……。どうして?」
「尚子さん、べろんべろんだから送って行けって、ママが」
「そうなんだ」
突然、尚子は前かがみになって口を押える。そのまま、急いでトイレに駆け込んだ。
「ご迷惑おかけしました」
トイレで嘔吐し、少しは気分がましになった尚子は、大森の前で深々と頭をさげた。
「いや、うれしい……」
「え?」
「い、いや。迷惑だなんて」
正直な気持ちをつぐみ、大森は尚子を気づかう。
「大丈夫? もう1杯、水、くんでこようか?」
「うううん、自分でします」
「そう。じゃあ、ボクは」
長居もはばかれるし、あまり遅くなると久子が勘ぐる。大森は尚子の部屋を出ようと立ちあがった。
「大森さん」
「なに?」
「もう少し、いっしょにいてもらっていいですか」
「え?」
「一人ぼっちはきらいです」
淫靡な眼差しで尚子は大森を見つめる。惑乱をあおる視線に、大森の理性はたががはずれる。
「な、尚子さん」
大森は尚子を抱きしめる。尚子は大森を見あげてあごを突き出し、ゆっくりと目を閉じた。
「きのうは遅かったのね」
翌朝、寝室から出てきた大森に久子は声をかける。
「どこにお出かけ?」
「いや、ちょっと飲みに。偶然、知り合いに会ってさ。そのあとハシゴ」
「ふ~ん。帰ってきてから、すぐにお風呂に入ったの?」
「え?」
「夜中に音がしてた」
「あ、ああ……」
大森は洗面所に向かう。久子は、それ以上、問い詰めなかった。
唇を重ね合ったあと、尚子は身体をずらして大森の股間に顔をうずめる。そして、ズボンの中から一物を取り出すと、舌を伸ばして舐りはじめた。
もはや大森にあらがう理由はない。尚子の口技で完全な勃起を果たした大森は、その場に尚子を押し倒す。そして、乱れたドレスを脱がせ、陰部にむしゃぶりついた。
「あん……、そこ、だめ」
尚子から甘艶な声が漏れる。大森はにじみ出る愛液をすすり、充血した肉ビラや陰核を探る。下着姿の尚子は我慢できないといった素振りで大森をあお向けに寝かせ、馬乗りになった。
「挿れるね。いいでしょ」
大森は黙ってうなずく。尚子は下着を脱いで大森に手をそえ、潤った膣壺の中にいざなった。
またがって腰を振りながら、尚子はブラジャーをはずした。露呈された乳房を見て、大森の興奮は、より高まる。
丸く実った両の乳塊は、尚子がのけぞると顔が隠れてしまうほど実り、律動に合わせてタップタプと揺れる。桃色の乳首が惑い、部屋の明かりを受けて光沢を放っていた。
大森は手を伸ばして胸乳を揉む。手のひらが吸いつくほどしっとりとした肌理。力を加えれば、指が食い込むほど柔軟だ。
「やああん、いい、ステキ」
尚子は舞い躍りながら湿った声をあげた。大森はそんな尚子を見つめながら、欲情に合わせて腰を突き上げる。
やがて大森は、限界の到着を尚子に告げる。
「イクよ、イキそうだ」
「出すの?」
「うん」
「いいわよ。でも、中はだめだから」
尚子は大森から降りると、いままで胎内に埋没していた肉棒をほお張る。舌を絡ませながら首を上下させ、前かがみになって抜き差しをくり返す。
大森は、そのまま尚子の口腔に、ほとばしりを放ったのだった。
「よかったなぁ」
歯を磨きながら、大森は回想する。
妖艶なしぐさに、神々しいほど整った肢体。内部の締めつけは強く、蜜の量も多い。そして、積極的に求めてくる行為に、大森は感動すらおぼえた。
「これを機会に……。けど、かなり酔っていたから、おぼえているかな?」
「あなた、はやく朝ごはん済ませて」
久子の声が、大森を現実に引き戻す。
「あいつとは大違いだ」
大森はうがいをし、冷たい水で顔を洗って台所に向かった。
夜、尚子とのことが忘れられない大森は、仕事を終えた足で店に向かった。
「あら、大森さん。連日のお出まし」
迎えてくれたママがいい、となりで尚子が笑みを浮かべていた。
「きのうは送っていただいて、ありがとうございました」
おしぼりを差し出しながら尚子はいう。
「いや、たいしたことじゃない」
「わたし、変なこといったり、したりしませんでした? 記憶がなくて」
やはり尚子はおぼえていない。大森は落胆してしまう。
行為の最中、尚子は何度も大森のことを好きだといった。貫き通した感触が最高だ、とも口にした。終わったあと、またシたいともいっていた。
すべては酔いにまかせた虚言だと思うと、やるせない気持ちになる。
ほかの客が訪れる。尚子は、その客の前に立つ。大森は一人でグラスをかたむけ、苦いウイスキーをすする。
「きのうは大変だったでしょ。あの子、酒癖が悪いから」
水割りのお代わりをつくるママがいった。
「いや、別に……」
「でも、どんなに酔っていても、冷静なところは残しているの。記憶が飛んでいても、ところどころはおぼえているはず……」
そのとき客がママを呼ぶ。交代で尚子が大森の前に立つ。
「きのう……」
尚子は、そうつぶやいて口をつぐんだ。
「きのう?」
「記憶がなくなったのは本当だけど、かんじんなことはおぼえてる」
そういいながら、尚子は大森を上目づかいで見る。
「あんなこと、ほかのお客さんにはしないんだから。大森さんだけ」
おぼえている。尚子は自分との交わりを記憶に残している。しかも、身体を許すのは自分だけという。
「ねえ、大森さん」
「ん?」
「わたしと大森さんって、相性がよさそう」
「そうなの?」
「うん。とくに身体の相性。だから……」
「だから?」
尚子はママと客が聞き耳を立てていないのを確認し、大森の耳元でささやいた。
「続きがしたい」
「いいの?」
「うん。子どもは実家に預けるから」
「じゃ、じゃあ」
「ん?」
「次の日曜日。うちも女房と子どもが留守なんだ」
「本当?」
「ああ」
「じゃあ、約束して」
尚子は右手の小指を差し出す。大森は自分の小指を絡める。
「ゆ~びき~りげんまん、ウソついたらハリ千本の~ます」
昼下がりの布団の上で、大森は自分にまたがっている尚子を見つめる。肉づきのいい太ももを開き、短いスカートをまくりあげた尚子は、艶然とほほ笑みながら着ているセーターを脱いだ。
「黙っていればバレないわよ。さ、楽しみましょ」
尚子はそういって背中に手をまわし、ブラジャーのホックをはずした。
久子は息子を連れて買い物に出かけている。尚子の子どもは夜まで戻ってはこない。
乳房を露呈させた尚子は前かがみになる。そして大森のシャツのボタンを一つ一つていねいにはずし、肌着を首まであげると米粒大の乳首に舌をはわせた。
「あ……」
唇ではさまれ、クチュッと吸い込まれた瞬間、大森はだらしなく声を漏らしてしまう。
「気持ちいいの? 感じるの?」
尚子の問いかけに、大森は黙ってうなずいた。
「かわいい。女の子みたい」
大森のシャツと肌着を脱がし、乳房を押しつけながら尚子は顔をずらす。そして大森のズボンと下着を脚から抜くと、すでに膨張している一物に唇を当てた。
ずりゅっという感触と同時に、温かな体温が男根の芯まで伝わってくる。尚子は内頬の粘膜でおおいながら、螺旋を描いて舌を絡みつかせた。
尚子の小さな口内で、大森は極限まで膨張する。びくびくと脈打ち、尖端からは先走り汁がにじみ出ていた。
根元までほお張った尚子は、ゆっくりと大森の中ほどまで抜き取り、ふたたび顔面を押しつける。その間も舌の動きは止まることなく、大森の敏感な部分を探り続けた。
尚子の動きが早くなる。
「そんなにしたら、出ちゃうよ」
「お口だけでイクのはいや?」
「いやじゃないけど」
「じゃあ、最初は飲ませて」
全身を使って尚子は大森を責めた。吸いつきを強め、よだれをたらしながらぢゅぼちゅぽと抽送をくりかえす。
大森は尚子の乳房に手をのばし、わしづかみにしながら暴発をこらえる。
「あ……」
全体をふくみ、舌がぐるんとサオをなぞった瞬間、大森は果ててしまった。
尚子は吐き出される粘液を受け止め、最後の1滴を搾り出すと大森を抜き取る。そして、そのままコクリと喉を鳴らして飲み干した。
「ふふ、大森さんのおいしい」
尚子は立ち上がり、スカートとパンティを脱ぐ。
「さ、今度はわたしを気持ちよくさせて」
あお向けに横たわる尚子の両脚をひろげ、大森は秘裂にむしゃぶりつく。ゆるく閉じた肉唇を舌でこじ開け、割れ目を上下に舐る。
「あああん、そこ、やん、感じちゃう!」
大森の頭を押さえつけて尚子はよがった。鼻の先で淫豆をくすぐりながら、大森は吸いつき、なぞる。
「やん、もう、あああん、イキそう、イッちゃうう!」
尚子は、大森の愛撫で一度目のアクメを得る。
「大森さんのいじわる」
恥じらいながらすねた素振りを見せる尚子。頭の血管が破裂しそうな興奮をおぼえた大森は、尚子を押し倒しておおいかぶさったのだった。
「あ、くん……!」
一気に根元までめり込んでくる感慨に、尚子は唇をかみしめてしまう。
膣内は十分に潤い、抜き差しするたびにぴちゅくちゅと摩擦の音がする。尚子の内部はるつぼと化し、粘りのある潤滑液をあふれさせながら締めつける。
尚子の温度とぬめり、膣襞のぜん動を感じ取りながら、大森は強く腰を打ちつけた。
「ああああん、だめぇ、壊れちゃう、変になっちゃう!」
いったん抜き出した大森は、尚子を腹ばいにして後ろから貫く。尚子は布団のシーツを握り、身体を伸縮させながら大森の攪拌を甘受する。
「だめ、いやん、すごい、すごい」
「気持ちいいよ、尚子さん」
「尚子って呼んで、尚子って」
「尚子」
「やん、大森さん、いい、あん、バカになる、バカになるぅ!」
大森はふたたび尚子を正常位に戻す。尚子は両脚を掲げて大森の腰にからめる。子宮の入り口まで到達する突き入れ。下腹の内臓が押し上げられ、口を大きく開けて淫気を吐く。
歓喜のたかまりに合わせ、尚子の内部はますます圧力を増した。大森は、やわらかくて強い圧迫を押し返すように、勢いをつけて振幅を広げる。
「だめ、もうダメ、イクの、イッていい?」
「オレもイキそうだ」
「出して。このまま出して」
「いいのか」
「いいの、きょうは大丈夫。あああああん、やだやだ、もうだめぇ、イク、イッちゃうう!」
腰に絡まる脚の力が強くなる。抜き出すことのできない大森は、そのままビュビュッとザーメンを吐き出す。尚子は精子を受け止めながら、何度も軽いけいれんをくり返したのだった。
布団の上で身を起こし、大森はマッチをすってタバコに火を着けた。
「わたしにもちょうだい」
寝そべった尚子はねだる。大森は自分の咥えていたタバコを尚子の口に入れ、新しい1本に火を着けた。
――ピンポーン。
そのとき呼び鈴が鳴った。虚脱している尚子は、身動きできない。このまま無視すればいい。大森は思うが、呼び鈴はしつこく何度も鳴らされる。
「もう」
尚子は気だるく立ち上がり、下着をつけないままガウンをはおって玄関にいく。
「あ……」
「この盗人ネコ!」
怒号とともに、どかどかと入り込んでくる女。
「ひ、久子」
咥えていたタバコを口から落とす大森。久子は腕を組んで仁王立ちになり、早く服を着るよううながした。
尚子と大森の関係を怪しんだ尚子は、近所の主婦と結託し、二人の行動を調べあげた。大森が尚子の店に足しげく通い、タクシーで送った夜のことも調査済みだ。そこで久子は、子どもを連れて留守にすると偽り、浮気の現場を押さえつけたのだ。
2日後、尚子は夜逃げのように団地を去った。大森には、ふたたび退屈な日常が舞い戻ってきた。
- 【長月猛夫プロフィール】
- 1988年官能小説誌への投稿でデビュー。1995年第1回ロリータ小説大賞(綜合図書主催)佳作。主な著作『ひとみ煌きの快感~美少女夢奇譚』(蒼竜社)/『病みたる性本能』(グリーンドア文庫)/『19歳に戻れない』(扶桑社・電子版)ほか。
この記事の画像
関連キーワード
 Linkage
関連記事
Linkage
関連記事
-

昭和官能エレジー第20回「深夜ラジオのメッセージと再会」長…
-

昭和官能エレジー第19回「哀願をくり返した通相手の少女」長…
-

【昭和官能エレジー】第18回「仕組まれたポルノ女優――中に…
-

昭和官能エレジー第17回「別れを切り出された浅はかな男」長…
-

昭和官能エレジー第16回「童貞男子を翻弄した謎の淫乱少女」…
-

【昭和官能エレジー】第15回「女のたずねてくる電話ボックス」
-

昭和官能エレジー第14回「凌辱されたタバコ屋の女子大生」長…
-

昭和官能エレジー第13回「団地妻の淫惑」長月猛夫
-

昭和官能エレジー第12回「拾ったフィルムに映されていた緊縛…
-

【昭和官能エレジー】第11回「歌手崩れの男に溺れたご令嬢」
-

あの週刊大衆が完全バックアップした全国の優良店を紹介するサイト
 FANZA新着動画
特選素人娘マル秘動画
FANZA新着動画
特選素人娘マル秘動画
-

【VR】心地よい囁きで脳イキが止まらない… 不眠症のボクに…
-

子宮直撃!!ガンガン突かれてピクピク痙攣奥まで中出しベスト
-

母さんとしてくれる?禁断のSEXを選んだ母、背徳感が母と子…
-

誘惑するのはまさかのドスケベお姉さん
-

大人のAVベストセレクション vol.24 平成の女教師ド…
-

新・大人のAV 官能ドラマ傑作選vol.27 9作品本編ま…
-

エグい程イキ狂うおばさんの不倫SEX
-

突然の大雨でズブ濡れになった濡れ髪と透け下着で無自覚にデカ…
-

シロウト人妻ナンパ中出し 奥さん、これからショートタイム不…