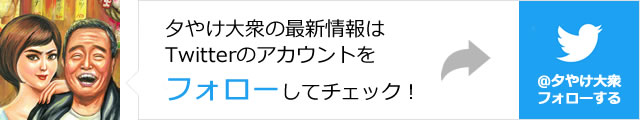Catch Up
キャッチアップ
Catch Up
キャッチアップ

この官能小説は、現在50代から60代の方々の若かりし時代を舞台背景にしています。貧しかったけれど希望に満ち溢れていたあの頃、そこには切なくも妖しい男と女の物語が今よりも数多く存在しました。人と人とが巡り合う一瞬の奇跡、そこから紡がれる摩訶不思議な性の世界をお楽しみください。 編集長
「見習いの犠牲になった二十歳の仲居」長月猛夫
「こら! なにやってんな。もっとしっかり動かんかえ!」
「す、すんまへん、大将」
「こら、尾崎! この器、洗い直しや! こんな汚いのに料理盛れるかえ!」
「すんまへん、板長」
尾崎は中学を卒業すると、すぐに大阪ミナミの料亭へ住み込みで修業に入った。だが、要領の悪い尾崎は、常に怒鳴られてばかりだ。
朝は届いた野菜の下ごしらえをしてご飯を炊き、昼からは板前連中が行う仕込みの手伝いと洗い物。客の入った夜からは、もっぱら皿洗いに徹する。休日は日曜だけ。
住み込みの部屋はアパートの個室だったが、トイレと洗面、流しは共同で、昼間でも窓から陽のささない3帖一間。押し入れもなく、湿気で壁紙都畳がふくれあがるような部屋だった。
そんな、あわただしい毎日を送る尾崎を見守る一人の女性がいた。仲居の美代子だ。
美代子も中卒で田舎から出てきて、住み込みで働いている。年齢は20歳。
「尾崎くんは、なんで板前になったん? 将来、お店持ちたいとか?」
店開け前の休憩時間。ほかの板前や仲居が花札に興じているわきで、尾崎は所在なげに座っていた。そんな尾崎に美代子は話しかける。
「ボク、そんなんちゃいますねん。ウチは父親が早ように死んでしもて。ボク、5人兄弟の2番目なんです。兄貴は頭がええから高校に行かしてもろたけど、ボクは頭悪いし弟と妹養うカネいるさかいていうて、働きに出されたんです」
「そんで、この店に?」
「死んだ親父の知り合いが口きいてくれて。腕に職つけたら、どないしてでも生きていけるっていうて。そやけど、ボク、どんくさいから……」
尾崎は一気に話した。
「そうなん。うっとこは反対や。お母ちゃんが先に死んでしもた。お父ちゃんは新しいお母ちゃんと結婚したけど、ウチとは仲が悪て。学校出てから家、飛び出した」
「そうなんでっか」
「うん。弟がおってな。ウチと違て勉強できるさかい、上の学校に行かせたかった。そやけど、新しいお母ちゃんは、おカネもないのに勉強することないっていうねん。そやから、ウチが仕送りして高校に行かせてんねん」
その日をきっかけに、美代子は何かにつけて尾崎に話しかけるようになった。休みの日には、尾崎の部屋を訪ねて掃除や洗濯をかって出ることもある。
「美代子さん、そんなんしてもろたら悪いわ」
尾崎は恐縮していう。
「かめへん、かめへん。そうや、お給料出たさかい、外でご飯食べへん? おごるさかい」
「そんなん……」
「ええから、ええから。給料日あとの休みの日ぃくらい贅沢しても罰当たれへんわ」
尾崎の給料は月7万円。そこから部屋代が1万5000円引かれる。
仕事の日は店からまかないが出されるものの、休日の食費は自分持ちである。少ない給料から母親に送金しているので、給料日前に食費が足りなくなるのもしばしばだったし、給料が出たからといって好きなものを食べられる余裕はない。
そのことを美代子は知っていた。だからこそ、尾崎を誘ったのだ。
「な、行こ」
美代子はちゅうちょする尾崎の手を握って、半ば強引に部屋から連れ出した。尾崎は美代子の手の冷たくてやわらかい感触に、強い緊張をおぼえてしまった。
「あんた、最近、見習いの尾崎と仲ええらしいな」
ある日、二人の仲を勘ぐった仲居頭の佳代がいった。
「部屋にいったり、休みにご飯食べにいったりしてるらしいやないの」
「それくらい、アカンのですか?」
「別にアカンことないけどな。そやけど、あの子はまだ見習いや。変に色気づいて仕事に身ぃ入れへんようになったら困る。まあ、聞くところによると、まだ深い仲にはなってないようやけど」
「だれが、そんなんいうてるんですか」
「おんなじアパートの板前や。あんなボロやろ。変なことしてたら音も声も筒抜けやさかいな」
「深い仲っていうても、尾崎くん、まだ子どもやないですか」
「もう16や。チンコに毛ぇも生えてるやろ。十分や。ウチが女になったんも、それくらいやった」
仲居頭の高慢な態度に、美代子は黙ってしまう。
「な、ええか。あの子にとって、いまは仕事に頑張るときや。見習い終わって、包丁でも握れるようになるまで女はご法度や。あんたも、それくらいわかるやろ」
だが美代子は返事をせず、身をひるがえして立ち去った。
「ま、待ちいな……」
「なんや佳代、どないしたんや」
そのとき店主の山口が姿を見せる。
「あ、大将、あの子、最近、尾崎となんかややこしいそうでっせ」
「ふ~ん」
山口は美代子の後姿をまじまじとながめる。
「ま、ええやないか。あの子と尾崎は4つも離れてる。美代子には弟がおるから、尾崎のこと、弟みたいに思てるんやろ」
「そうでっかぁ?」
「そんなことより、きょうの宴会の用意できてるんか。お前も、こんなとこでごちゃごちゃいうてるヒマないやろ」
山口は、そういい捨てて、その場を去る。
「大将は、美代子に甘いわ。ひょっとして、狙てるんちゃうか」
佳代はつぶやきながら、宴会場へ急いだのだった。
やがて12月が訪れた。宴会シーズンに入ると日曜でも休日にならない。次の休みは大晦日前日の30日だ。
尾崎も美代子も多忙な毎日を送る。それは、どの従業員も同じで、日を追うごとにストレスがたまってくる。割を食うのはもっとも下っ端の尾崎だ。
「尾崎、さっさとせんかぇ! 皿、足らんやろ!」
「すんまへん」
「ザルはどこや、まだ洗てないんか!」
「すんまへん、すぐに」
食器だけでなく、調理器具も洗って板前に差し出す。タイル張りの床は濡れ、長靴でも足元はおぼつかない。
「尾崎、なんやこれ!」
「え?」
「ザルの目が詰まっとるやないか」
「ええ?」
「ここや、見てみぃ!」
板前にいわれてザルをのぞく。たしかに数か所だけ目詰まりしている部分があった。
「すんまへん、すぐに!」
「ボケ! 洗いもんぐらい、ちゃんとせえや!」
板前はザルを尾崎に投げつけた。それをよけようとした尾崎は、足をすべらせて転倒し、調理台の角で頭を打つ。
「キャー!」
悲鳴をあげたのは、出来上がった料理を取りに来た美代子だった。
尾崎の額は切れ、血がにじみ出ている。意識が薄れ、尾崎はその場に昏倒する。
「尾崎くん! だれか救急車」
騒ぎを聞いて佳代が駆けつける。彼女は尾崎のようすを見ていった。
「この程度の傷やったら救急車ら呼ばんでも大丈夫や。騒ぎになったらお客さんも迷惑やろ」
「そ、そやけど」
「奥で消毒してクスリ塗って寝かしとき。大将、それでよろしいな」
佳代にいわれて、山口は大きくうなずく。美代子は、心配そうに尾崎の顔をのぞき込む。
「そないに心配やったら、美代子、アンタが介抱したらええわ。あとのことは大丈夫やさかい」
「わかりました」
美代子は尾崎の身体をかかえ、厨房を出ていく。そのようすを、佳代は意味ありげな表情で見つめていた。
「大丈夫? 痛ない?」
控室に寝かされ、意識を取り戻した尾崎に美代子はいった。
「あ……、平気です。仕事に戻らんと」
尾崎は身体を起こそうとした。それを美代子は制する。
「アカンて、まだ血ぃも止まってないのに」
「そやけど」
「大将も寝かせとけていうてた。尾崎くん、最近、満足に寝てないんとちゃうの?」
「いえ、ボクがどんくさいだけです」
美代子は尾崎の背中を支えて横たわらせる。尾崎は天井をながめ、大きくため息をついた。
「ほんま、ボクはアカンわ。こんなんやったら足手まといになるだけや。迷惑かけるだけや」
「そんなことない。みんな最初は、そんなもんや」
「そうでっか? ボクも包丁握れるようになれるんかな」
「大丈夫、きっとなれる」
そのとき、傷が痛むのか尾崎は表情をしかめる。
「どないしたん? 痛いん?」
心配した美代子は前屈みになって尾崎の顔をのぞきこんだ。
「なにしてんの?」
そんな美代子の背後から、だれかが声をかけた。佳代だった。
「こんなとこで口吸いか。ほんま、いやらしい」
驚いて振り向く美代子。
「ちゃいます。うちは尾崎くんが痛がるから」
「言い訳は聞きとうない。ほら大将、うちのいうたとおりでっしゃろ」
「ほんまや」
佳代のうしろから山口が姿を見せた。
「まだ仕事の最中やいうのに、しかも見習いの分際で。尾崎、お前はクビや」
「そんな! 大将、堪忍してください。クビだけは」
尾崎は身を起こしていう。
「大将、尾崎くんはなんも悪ない。辞めさせるんやったらウチを!」
美代子は訴える。
「やかまし! 尾崎、痛いのが収まったら荷物まとめて出ていけ。ええな」
そういい残して、山口は場をあとにする。佳代は薄ら笑いを浮かべながら、山口につづいた。
その日の夜、店が終わると、山口は事務室で売り上げの計算を行っていた。畳敷きの4畳半に文机を置き、札や小銭を数えながら帳面をつける。
割烹着を脱いだ山口は、肌着とステテコ姿。部屋の隅では、電熱のストーブが赤々と熱を放っていた。
「大将、よろしいですか」
ソロバンをはじいている山口の背後に、美代子が声をかける。山口は咥えていたタバコを灰皿に置き、振り返った。
「なんや」
「大将、このとおりです」
美代子は正座し、畳に額をすりつけて土下座した。
「このとおりです、尾崎くんを許してやってください」
「そんなこといいにきたんか」
「はい、ウチにできることやったらなんでもやります。そやさかい、尾崎くんをこれまでどおり、お願いします」
山口は机に向き返り、煙草を口にはさむ。
「あかん、あかん。いっぺん決めたこっちゃ。なんぼケガしたていうてもやな、仕事中に女とイチャイチャするようなヤツは」
「イチャイチャなんかしてません。誤解です。ウチは痛がる尾崎くんが心配で……」
その言葉を聞いて、山口はふたたび美代子を見る。
「あのな、尾崎を辞めさせるのは、きょうの一件だけとちゃうねん。あんなどんくさいやつ、いつまでも店に置いとかれへん。そやから辞めてもらうんや」
「大将」
美代子は畳に手をついたまま、山口を見あげた。
「古い知り合いに紹介してもろたから雇たけど、いまだに満足に洗いもんもでけへんし、下ごしらえさせてもヘマばっかしや。あいつに料理はむけへん。さっさと辞めさせて、違う仕事に就かせたほうが、あいつのためや」
「まだ、ここにきて1年もたってないやないですか」
「4月に雇て、もう8か月や。それくらいたったら、使いもんになるかどうかくらいわかる」
そういいながら、山口は美代子の肢体をながめた。
絣の着物の襟もとがゆるみ、白い素肌がかいま見える。尻から太ももにかけての曲線が、艶めかしく丸まっている。着物の裾がかすかにまくれ、足袋との境に細い足首がのぞいている。
「そ、そやけど、まあ、お前がそこまでいうんやったら、考えなおさんでもないけどな」
「ほんまですか!」
美代子は顔に喜色を浮かべて身を乗り出した。
「美代子」
「はい!」
「お前さっき、なんでもするっていうたな」
「は、はい……」
「たしか20歳やな」
「そうです」
「尾崎とは、やったんか」
「え……、そんなん……」
「尾崎以外とは……」
山口は美代子との距離を、徐々に狭めていった。
「ウチは、まだ……」
「オボコかいな。それやったら、わしが最初の男になっちゃろやないか」
山口は美代子におおいかぶさる。美代子は身をねじって逃げ出そうとする。しかし、山口の体重を押しのける力は持ち合わせていなかった。
「お前さえ、わしのいうこと聞いたら尾崎は助かるんや。な、いうこと聞け。悪いようにはせえへん」
美代子の耳もとで山口はささやく。
「ほ、ほんまですか」
「ほんまや、なんやったらお前を仲居頭にしてもええ。佳代は気が利かんし、評判も悪い。その点、お前は器量もええし、客あしらいもうまい」
「大将」
「美代子、わしの女になれ。悪いようにはせえへんさかい」
着物の襟から山口は手を差し入れ、美代子の乳房を揉む。ゴツゴツした手のひらと指の感触を受け止めながら、美代子は唇をかむ。
「美代子、こっち向け」
目を閉じ、唇を閉ざした美代子は山口の方向に顔を向ける。山口は乾いた唇で、美代子の口をふさいだ。
悪臭が口から鼻に抜ける。わしづかみにされた乳房は乱暴にまさぐられている。
山口は着物の裾を割り、手を入れる。
「うん……」
山口の指先が下着をくぐって敏感な部分にふれたとき、美代子はいっそう固く唇をかんだ。
山口は美代子をあお向けに寝かせる。そして帯を巻いたままの状態で、裾を大きく左右にひろげた。
美代子の白い脚があらわとなる。部屋の明かりを受けて光沢を放つふくらはぎから太ももを、山口は荒い息を吐きながら舐める。
「ええ味や」
顔は美代子の股間に至る。山口は白い木綿の下着に手をかけ、一気にかかとまでずらした。
両手で顔をおおう美代子。山口は薄い茂みの向こうにある肉の裂け目を淫猥な表情で見つめた。
「形も色もええあんばいや。男、知らんっちゅうのはほんまやな」
肉裂に顔を押しつけ、舌でなぞる山口。泣き出しそうな感情を押し殺し、美代子は恥辱に耐える。
さんざんしゃぶりつくした山口は膣口をひろげ、右手の中指をめり込ませた。
「ひいぃ!」
美代子は思わず声をあげてしまう。その声に自分自身が驚きをおぼえ、手のひらで口をふさぐ。
山口は秘部を弄りながら身体を美代子にかぶせ、襟に手をかけて肩までずらす。そしてブラジャーを下にずらし、露出されたつぶさにむしゃぶりついた。
「はふ、はふ、はふ……、ええ味や、極上や」
乳首を吸い、房を揉む。ステテコとブリーフの中で、山口の肉柱は痙攣をくり返しながら強張っている。
「もうええやろ、挿れるぞ。痛いのんは初めだけや」
下半身のすべてを脱ぎ捨て、山口は怒張の先を美代子の入り口にあてがった。そのまま腰を押しつけ、根元まで突き入れる。
「い、いた……!」
破瓜の痛みが美代子の全身を襲う。その激痛に耐えながら、美代子は涙を流し、かみしめた唇からは血がにじんだ。
一部始終を尾崎は見ていた。
出て行けといわれたものの、頭をさげれば考えを改めてくれるかもしれない。そう思って、山口のいる事務所をたずねた。
しかし、尾崎が目の当たりにしたものは、凌辱される美代子の痛々しい姿だった。
「オレのために、オレのために」
尾崎は美代子を最後まで見守ることができず、脱兎のごとく逃げ出した。そのままアパートに戻り、荷物をまとめる。
「美代子さん、ごめん、ごめんなさい」
少ない荷物をカバンに詰めながら、尾崎は何度もあやまる。
「ごめんなさい、ほんまごめんなさい」
涙で目の前がにじむ。
師走の深夜。どこからかノラ犬の遠吠えが聞こえてきた。
- 【長月猛夫プロフィール】
- 1988年官能小説誌への投稿でデビュー。1995年第1回ロリータ小説大賞(綜合図書主催)佳作。主な著作『ひとみ煌きの快感~美少女夢奇譚』(蒼竜社)/『病みたる性本能』(グリーンドア文庫)/『19歳に戻れない』(扶桑社・電子版)ほか。
この記事の画像
関連キーワード
 Linkage
関連記事
Linkage
関連記事
-

【昭和官能エレジー】第41回「ビデオからあらわれた不思議少…
-

【昭和官能エレジー】第40回「友人の姉の裏切り」長月猛夫
-

【昭和官能エレジー】第39回「見られてしまった教室での痴戯…
-

【いいおっぱいの日!特別コラム】「日本近代史におけるおっぱ…
-

【昭和官能エレジー】第38回「同棲相手との40年ぶりの再会…
-

【昭和官能エレジー】第37回「捨てられた女・捨てられた男」…
-

【昭和官能エレジー】第36回「人生をあきらめた細い身体の女…
-

【昭和官能エレジー】第35回「東京から流れてきた女」長月猛夫
-

【昭和官能エレジー】第34回「追い出された女との束の間の同…
-

【昭和官能エレジー】第33回「留年大学生を男にした下宿屋の…
-

あの週刊大衆が完全バックアップした全国の優良店を紹介するサイト
 FANZA新着動画
特選素人娘マル秘動画
FANZA新着動画
特選素人娘マル秘動画
-

最高!スケベマダムさんですな
-

マダムがエッチにイクオーガズム
-

させて頂きますよ!ハメハメトレイン出発します
-

あなたのペニスを求めています。エッチだから
-

明らかに淫らですスケベマダム
-

【VR】「妻の味を聞かせてください。」夫から差し出された人…
-

なっちゃん
-

くるみ
-

ゆきの 2