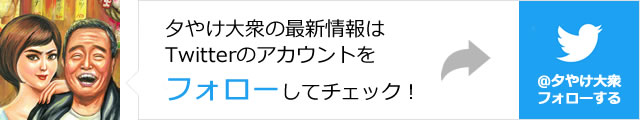Catch Up
キャッチアップ
Catch Up
キャッチアップ

この官能小説は、現在50代から60代の方々の若かりし時代を舞台背景にしています。貧しかったけれど希望に満ち溢れていたあの頃、そこには切なくも妖しい男と女の物語が今よりも数多く存在しました。人と人とが巡り合う一瞬の奇跡、そこから紡がれる摩訶不思議な性の世界をお楽しみください。 編集長
【見られてしまった教室での痴戯】長月猛夫
11月初めの祝日、中西は駅で加奈子を待っていた。
山口加奈子は中西の同級生だ。高校に入学したとき、中西はとなりのクラスの加奈子を初めて見たときから好意をいだく。2年で同じクラスになると、中西と仲のいい友人グループに加奈子を含めた女子も加わり、徐々に距離を縮めていった。
夏休みには、そのグループで海水浴に行き、盆踊りや夏祭りにも出かけた。9月に新学期がはじまり、10月には文化祭に体育祭。
このころになると、グループの男子は中西の気持ちを察してくる。
「お前、山口のこと好きなんだろ」
「さっさと告白しちゃえよ」
「山口もまんざらじゃないはずだよ」
そんなふうに、あおる友人もいた。
「や、山口さん、こ、今度の祭日に映画に行きませんか」
中西は勇気を出して誘い、加奈子も快く応じてくれた。
駅前の空は高く澄みわたっていた。風が吹くと寒さも感じられるが、陽光はポカポカとした暖かさで包んでくれる。
電車が到着すると乗客たちが改札を通り、駅員の切符を切る音がカチカチとひびく。
はきなれたスニーカーに、少し色の落ちたジーパン。少し厚みのあるシャツはズボンの中に入れられている。
そんな姿の中西は、約束の時間の30分前に待ち合わせ場所に到着していた。
「まだかなぁ」
中西は左腕にはめた腕時計を見る。針は12時40分を指している。
「あと20分かぁ」
時間を確認して時計から目をあげると、小走りに駆けてくる女の子の姿が見えた。加奈子だった。
「ご、ごめんなさい。待った?」
息せき切って走ってきた加奈子は、中西の前に立つと、そういって謝る。
「ううん、今きたとこ。それに、まだ約束の時間じゃないし」
「うん、楽しみにしすぎて早くきちゃった。そうしたら中西くんの姿が見えて」
加奈子は笑みを浮かべ、少し背の高い中西を見あげた。
加奈子のいでたちは、ひざが隠れるスカートに光沢のあるブラウス。手には小さなバッグを持っている。制服のときと違い、大人びて見え、しかも薄い化粧を施している。
いつもと変わらないスタイルの中西は自分を恥じながらも、じっと加奈子を見つめてしまった。
「え? なに? どこかおかしい?」
加奈子は首をひねって自分の姿を確認する。
「おかしくない、絶対におかしくない」
中西はあわてて否定する。
「よかった」
言葉を受けて加奈子はほほ笑む。その表情を見て中西は、キュッと締めつけられる胸の痛みと、多幸感が身体中にひろがるのを知った。
切符を買って改札を抜け、ホームのベンチに座って電車を待つ。
クラスメートになって半年がたち、学校では他愛のない会話をはずませる。しかし、ほとんど二人きりになることはなく、いつもだれかが一緒にいる。
二人で話す機会があったとしても、ほんの数分くらいのものだ。
だが、この日は違う。1時から許される限りの時間をともに過ごす。6時に加奈子の家に送り届けたとしても5時間だ。
映画を観て、お茶を飲んで、何かで時間をつぶして、この駅に戻ってくる。そのあいだ、いったい何を話せばいいのか。
中西は迷う。
「中西くん」
「え?」
「なに考えてるの?」
思いを巡らせていた中西に加奈子はたずねた。
「い、いや、別に……」
「中西くん、映画ってよく行くの?」
「ううん、めったに」
「わたしも久しぶり。きょうは何を観るの?」
「え、ええっと……」
初めてのデートに映画を選んだのは、上映中に話をしなくて済むからだ。しかも2時間近くとなり同士でいられる。そんな経験は、いままでにない。
とはいえ、何を観ようかなど考えてはいなかった。館内に入ることだけが目的であって、映画館に着いてから作品を選べばいいと思っていた。
「わたしね、観たいのがあるの」
「なに?」
「あのね、『人間の証明』。美和がよかったっていってた」
加奈子は友だちの名前を挙げていう。
「うん、じゃあ、それにしよう!」
迷いが払拭された中西は、思わず張り切った声を出してしまった。
上映時間に間に合った中西と加奈子は、窓口でチケットを購入して入館する。話題の映画ということもあって観客は多かったが、幸いにも座席は確保できた。
ざわついていた館内は、上映開始のブザーに合わせて静かになる。ステージ上のスクリーンには幕が張られ、客席の照明が落とされるとスポットライトが当たる。
しばらくすると、燕尾服を着た男があらわれ、ステージ隅に置かれたオルガンの前に座り演奏をはじめた。
ライトは男にそそがれる。男は曲を演奏し終えると、立ちあがって礼をし、ステージから姿を消した。
パラパラと鳴る拍手。この時点になると、話をする観客はいない。
スポットライトが消えて館内が闇に包まれる。スクリーンに向けて画像が映写されると幕が左右に開いて上映がはじまった。
作品は日本の敗戦にともなう悲哀を描いたものだった。日本の刑事とアメリカの刑事が、黒人男性の殺人事件を追う。
だが、中西にとっては映画の内容など、どうでもよかった。
中西は何度も、横に座る加奈子の表情をうかがった。加奈子は真剣なまなざしで銀幕を見つめている。ときには驚き、ときには悲し気な表情を浮かべて集中する。
加奈子の手は椅子のひじ置きにあった。少し手を伸ばせば触れられる位置にある。
中西は何度も加奈子の手に自分の手を重ねようと試みる。だが、最後の勇気を振り絞ることができなかった。
「テーマは重かったけど、見ごたえはあったよね。そう思わない?」
「うん、そうだね」
「戦争っていやね。平和な時代に生まれてよかった」
上映が終わり、映画館を出た中西と加奈子は喫茶店に入る。中西はコーヒーを注文し、加奈子はソーダ水を頼んだ。
「わたしのおじいさんもね、戦争で死んだの」
「そうなんだ」
「ママのお父さん。田舎に行くとね、軍服を着たおじいさんの写真が仏壇の上に飾ってあるの。けど、おばあちゃんはおじいさんのこと、あまり教えてくれない。ちっちゃいときに亡くなったから、ママもあんまりおじいさんのこと、知らないみたい」
ストローをもてあそびながらメロン色のソーダをかき混ぜ、唇にはさんで吸い込む。伏せたまぶたの周囲は長いまつげにおおわれ、まばたきするたびに上下する。
「中西くん、いままで観た映画で好きなのってなに?」
「え? オレは……、そうだなぁ」
中西が思い出すのは、子どものときに観た怪獣映画程度だった。
「わたしはね、『風と共に去りぬ』かなぁ。映画館じゃなくてテレビだったけど。ヴィヴィアン・リーがステキ。クラーク・ゲーブルがカッコよかった」
「ふーん」
中西はあいまいな返事をし、コーヒーをすする。口いっぱいにひろがる苦みを我慢し、のどに流し込む。
加奈子と映画の話などしたことはない。映画だけではない。音楽は何が好きなのか、休日に何をしているのか、どんなものに興味があるのか、まったく知らない。
もちろん、これまでに男とつき合ったことがあるのか、ということも。
もっと加奈子のことを知りたい。だれよりも仲良くなり、だれよりも加奈子のことを知っている男になりたい。
可能であれば、内面的なことだけでなく、身体のことも――。
それは17歳の男子として、ごく当たり前の欲求だった。
中西と加奈子の住む町の駅に戻ったのは午後6時だった。晩秋の夕闇は迫るのが早く、あたりはすっかり暗くなっていた。
中西は加奈子を自宅まで送る。商店街を抜けて住宅地に入ると、人の姿もまばらだ。
加奈子の家が近くなったとき、中西は突然、立ち止まった。
「どうしたの?」
不思議に思った加奈子はたずねる。
「や、山口さん……」
「なに?」
電柱に備えつけられた街灯が、加奈子の姿を浮かびあがらせる。中西は、そんな加奈子の姿を見ることができず、視線を落として口ごもる。
小首をかしげて中西を見守る加奈子。
「や、山口さん、あの……」
全身が熱くなる。苦しくなるくらい胸の鼓動が激しくなる。握りしめたこぶしに汗がにじみ、背中やわきの下でも汗が伝わり落ちる。
「あの、山口さん、あの……」
加奈子は黙って中西の次の言葉を待った。
「あの、もしよかったら、ボ、ボクと、その、つき合ってもらえませんか」
言い終えたとき、中西は脱力感を得る。
思いのたけは伝えた。あとは返答を待つだけだ。
「ごめんなさい」
しかし、加奈子の答えは意外なものだった。
「ごめんなさい。わたし、中西くんとはつき合えない」
驚きの表情で中西は加奈子を見つめる。
「どうして」
「理由はいえない。でも、中西くんのことはきらいじゃない。ううん、好きだと思う。きょうもすごく楽しかったし。でも……」
「でも?」
「ごめんなさい」
そういうと、加奈子は走ってその場を去る。残された中西はぼう然とたたずみ、加奈子の後姿を見送るしかなかった。
次の日、中西は学校へ行くのをためらった。いっそ休んでやろうか、とも思ったが、グズグズしているところを母親にせかされ、仕方なく登校する。
クラスの連中は、いつもと変わりがない。休憩時間にはグループが集まって、きのう見たテレビ番組の話や買ったばかりのマンガ雑誌の話で盛りあがる。
ただ加奈子が中西に話しかけることはない。それは中西も同じだ。
よもや断られることはあるまい。そう考えていた中西に、加奈子の態度はダメージが大きかった。
「あんなに楽しそうにしていたのに」
待ち合わせたときの姿、電車の中での会話、映画館で過ごしたひととき、喫茶店でのおしゃべり。
その一つ一つを思い出すことができる。
加奈子の表情、加奈子の声、加奈子の言葉、加奈子の放つオーラ。
どれをとっても、中西を拒絶するものではなかったはずだ。
「それなのに……」
釈然としない気持ちのまま、日は過ぎていった。
加奈子とデートに出かけてから20日がたった。その日は祝日だが、忘れ物に気づいた中西は学校にとりに行く。
休日の校内は人影もなく、ガランとしていた。グラウンドで汗を流す部活の掛け声や、音楽室で練習する吹奏楽部の楽器の音が聞こえるだけだ。
中西は、自分のクラスの教室に入ろうとした。そのとき、だれかが中にいるのに気づく。
「どうだ山口、気持ちいいのか」
「やあん、先生、ダメ、だれかきちゃう……」
「休みの日の教室になんか、だれもこねぇよ。それよりも、ほら、ほら、ほら」
「だめぇ、そんなの、やだぁ」
中西は扉を少し開け、すき間から中をのぞく。そこにいたのは体育教師の山中と加奈子だった。
加奈子は机の上に座ってスカートをまくり、大きく両脚をひろげていた。その前で山中はうずくまり、指で加奈子の股間をまさぐる。
加奈子は下着を着けていない。
「どうだ、ここがいいのか。それとも、ここか」
「いや、あああん、先生、だめぇ」
山中の弄りに合わせ、加奈子は甘い声をもらす。蜜がしたたり、山中の指を濡らす。
「だめ、やん、先生、ダメ、もうだめぇ!」
加奈子は達した。そのようすを見て、山中は品のない笑みを浮かべる。
「自分だけ先にイって。いけない子だ」
「だってぇ……」
「じゃあ、今度はオレを気持ちよくさせてくれ」
山中の言葉に加奈子はうなずき、机からおりると床にひざまずく。山中はズボンとブリーフをおろし、まだ力のこもらない男根を露出させた。
加奈子は口を開けて山中を呑みこむ。そのまま舌を絡ませながら、山中の淫欲をあおる。
「ああ、いいよ、山口。気持ちいい」
加奈子はうれしそうな表情で山中を見あげ、首を揺らして頭を振った。
山中の一物は徐々に肥大化する。加奈子の口腔がいっぱいになるほど怒張を果たす。それでも加奈子は抜き取ることなく、身体全体を使って刺激を加え続ける。
「山口、そろそろ挿れていいか」
「ふ、ふぁ、ふぁい、先生」
「じゃあ、机に手をついて尻をこっちへ向けろ」
加奈子は山中の言葉にしたがう。山中は加奈子のスカートをまくり上げ、少女の秘部に業物をあてがうと、ズブリと奥まで突き入れた。
「あああああ、先生、先生」
「いいのか、気持ちいいのか」
「は、はい、気持ちいい、先生の気持ちいい」
「そういえば、前の祭日に中西と二人で出かけたらしいな」
「は、はい」
「で、ヤったのか中西と」
「い、いいえ、シてません」
「そうだろうな。お前の身体はオレでなけりゃ満足できない。そうだろ」
「は、はい、そうです」
「ちゃんといってみろ」
「わたしは、山口加奈子は、先生のオチンチンでないと満足できません」
「そうだ、いい子だ」
セーラー服をあげ、ブラジャーをはずして胸を露呈させる。山中が腰を打ち付けるたびに胸乳が揺れる。
加奈子は机にうつぶせになり、山中の抽送を受け止めていた。山中はあからさまになった加奈子の乳房をわしづかみにし、勢いをつけて腰を振る。
二人の痴戯を中西は見つめ続けた。
加奈子のよがる声を聞き、歓喜にゆがむ表情を見つめる。唇をかみしめ、こぶしを握り締めながら、視線をそらさずに注視する。
「ダメ、ダメダメ、イク、イッちゃう」
「オレもだ。出すぞ、このまま出すぞ」
「うん、先生、ください。先生の、先生の精液をください」
「出すぞ、出る、あ……」
「うん、やん……」
山中は加奈子の中にほとばしりを放った。加奈子は何度も痙攣をくり返しながら、胎内を泳ぎまわる精虫の感触を得る。
一部始終を中西は見届けた。
涙で視界がにじみ、風景がゆがむ。かみしめた唇が切れ、血の味が口いっぱいにひろがっていた。
- 【長月猛夫プロフィール】
- 1988年官能小説誌への投稿でデビュー。1995年第1回ロリータ小説大賞(綜合図書主催)佳作。主な著作『ひとみ煌きの快感~美少女夢奇譚』(蒼竜社)/『病みたる性本能』(グリーンドア文庫)/『19歳に戻れない』(扶桑社・電子版)ほか。
この記事の画像
関連キーワード
 Linkage
関連記事
Linkage
関連記事
-

【いいおっぱいの日!特別コラム】「日本近代史におけるおっぱ…
-

【昭和官能エレジー】第38回「同棲相手との40年ぶりの再会…
-

【昭和官能エレジー】第37回「捨てられた女・捨てられた男」…
-

【昭和官能エレジー】第36回「人生をあきらめた細い身体の女…
-

【昭和官能エレジー】第35回「東京から流れてきた女」長月猛夫
-

【昭和官能エレジー】第34回「追い出された女との束の間の同…
-

【昭和官能エレジー】第33回「留年大学生を男にした下宿屋の…
-

昭和官能エレジー第32回「夏休みの幻 廃屋の女」長月猛夫
-

昭和官能エレジー第31回「年上少女の誘惑」長月猛夫
-

昭和官能エレジー第30回「女になれずに逝った少女」長月猛夫
-

あの週刊大衆が完全バックアップした全国の優良店を紹介するサイト
 FANZA新着動画
特選素人娘マル秘動画
FANZA新着動画
特選素人娘マル秘動画
-

個撮ナンパ #清楚で初心だと思ったら男好きな隠れビッチ女子…
-

いつでもドコでも即フェラ密着パイズリ4hours
-

毎日違うおっぱいに責められたい… 日替わり巨乳痴女SEXカ…
-

月野江すい プレミアムステージ初BEST8時間
-

「柔らか谷間に何度も出しなさい!」 射精直前の超快感パイズ…
-

奇跡の乳を持つ最胸シロウト 清原みゆう S1デビュー 1周…
-

男なら一度は抱きたい!高級ラウンジ嬢の超イイ女達とハメまく…
-

人妻自宅サロンBEST 底辺クズ隣人の汚らわしいデカマラに…
-

世界クラスのグラマラスボディ 気品溢れ出る本物CA 武田怜…