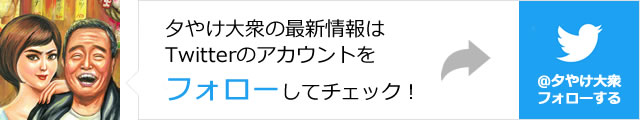Catch Up
キャッチアップ
Catch Up
キャッチアップ

この官能小説は、現在50代から60代の方々の若かりし時代を舞台背景にしています。貧しかったけれど希望に満ち溢れていたあの頃、そこには切なくも妖しい男と女の物語が今よりも数多く存在しました。人と人とが巡り合う一瞬の奇跡、そこから紡がれる摩訶不思議な性の世界をお楽しみください。 編集長
【妖しい酒とバーのマダム】長月猛夫
にぎわう繁華街の中にあって、迷路のような路地の奥にあるそのビルは、忘れ去られたようにひっそりとたたずんでいた。
ビルの前には、破れたチラシがベタベタと貼られた電柱。裸電球の街灯が灯り、まだ孵化して間もないであろう羽虫が飛び交っている。
レンガ造りのビルの入り口から、地下に通じる階段をおりる。無垢材でできた重厚な扉には店名を示すものが何もなく、もちろん看板も置かれていない。
杉下は極度の緊張にさいなまれながら、ドアのノブを持ってひねる。
カギはかけられていない。そのまま手前に引くと、ドアはギギッと微かな鈍い音を立てて開いた。
店の中は墨汁を流したように暗く、カウンターだけに照明が当てられている。バック棚には色とりどりの洋酒のボトル。その前に立つバーテンダーは、杉下を一瞥しただけで言葉を発さず、黙々とグラスを磨き続けていた。
店のホールはボックス席がいくつか置けそうなスペースだが、客が座れる場所は10席程度のカウンターだけ。
その片隅に女はいた。
「いらっしゃい」
女はスツールに腰をおろしたまま、杉下を見ていう。
「こちらへどうぞ」
女は杉下を、となりの席にいざなった。
足の震えをこらえ、脇に滴る汗を感じながら杉下は歩を進める。
かすかに漂う香水の匂い。どこからともなく流れてくるシャンソンの音色。
地の底から湧き出るような歌声に、ジジッジジッと針のこすれる音が混じっている。
杉下は激しく打つ心臓の鼓動を押し殺して、女の示す椅子に座った。
「何を?」
「あの……、ペルノーを」
「パスティスね」
女は薄い笑みを浮かべてバーテンに目配せをする。バーテンは軽くうなずき、磨いていたグラスをカウンターの下に置くと、棚から緑色のボトルを取った。
「きみは詩を読まないのかい?」
1年間の浪人の末、4月から通い始めた大学の昼休み。キャンパスのベンチで文庫本を開いていた杉下に、突然、声をかけてくる男がいた。
「詩? そんなには読まないし」
「ふ~ん、そうなんだ。じゃあ、ヴェルレーヌは知らないな」
「名前は聞いたことがあるけど、ボクはもっぱら日本のを読んでる」
「そうなんだ。おっと失敬。ボクは林田。きみは」
杉下は名前を告げる。
「杉下くん。じゃあ、萩原朔太郎も知らない?」
「あまり」
「朔太郎の詩に『死なない蛸』というのがある。ボクはあれを読んで、『山月記』に似通ったところがあると思ったんだけど、きみはどうかな?」
「『山月記』? 中島敦の?」
「隴西の李徴は博学才穎、天宝の末年、若くして名を虎榜に連ね、ついで江南尉に補せられたが、性、狷介、自ら恃むところ頗る厚く、賤吏に甘んずるを潔しとしなかった」
林田は杉下の前で立ったまま、『山月記』の冒頭をそらんじた。
「結局、李徴はトラになる。朔太郎のタコは自分を食べてしまうが、生命と魂は残る」
「それの、どこが似ていると」
「タコは知恵のメタファーだ。李徴は自分の才を生かせずに獣になる」
「そんなものかな」
林田は、ククッと笑って杉下の横に座った。
「きみは女を知っているかい?」
杉下は驚いて、林田の顔を見る。
「なんだよ、藪から棒に」
「知らないのか。早く知ったほうがいいよ。女を知ると世間を見る目が変わる。世間だけじゃない、人間を見る目も変わる。ほかの人間だけじゃない、自分自身もだ」
「けれど、相手がいないと話にならない」
「女なんてさ、カネさえ払えば、いくらでも抱ける」
「そういうのはイヤだ」
「ほう、なるほど。カネで春をひさぐような女はイヤだと」
「そういうわけじゃない」
「じゃあ、いいところを教えてあげよう」
林田はコートのポケットからメモ帳を取り出し、万年筆でサラサラと何かを書きつける。そして、1枚をビリビリと破って杉下に手渡した。
「この場所にあるビルの地下にバーがある。そこのマダムにすべてをまかせるんだ」
「いや、だから……」
「マダムはカネで身を売るような女じゃない。だからカネはいらない。ただし」
「ただし?」
「きみはペルノーを1杯だけ飲むんだ」
「ペルノー? なに、それ」
「アブサンの模造品だ。アブサンはご法度だから、いまは飲めない。ヴェルレーヌもゴッホもアブサンで身を滅ぼした」
林田はふたたび、クククッと押し殺した笑みを浮かべた。
「マダムの手ほどきで、きみの世界を見る目が変わる。じゃあ幸運を祈る」
林田はいい残して立ち去る。杉下はメモを手にしたまま、林田の後姿を目で追った。
「どうぞ」
小さなショットグラスに透き通った緑色の酒がそそがれ、杉下の前に差し出された。
「さ、どうぞ」
となりにいる女は、そうつぶやいて興味深い視線を杉下に送る。
杉下は恐る恐るグラスを持って口に運ぶ。薬草らしきにおいが鼻をつく。思い切って少しだけ口にふくむと、強烈な刺激が身体中をかけめぐった。
「う、うわ!」
杉下はグラスを置き、口をふさいでせき込んだ。バーテンは氷と水の入ったグラスを置く。その水を杉下は一気に飲み干すが、舌が焼けるような感覚は収まらない。
「ふふふ。ストレートは無理よね。ほら、こうすれば」
女は残った酒を水の中に入れる。酒は白く濁りながら、グラスの底に沈む。
「い、いや、水で薄めても、これは……」
「あら、ダメなの? お子ちゃまね」
女は小指を立ててグラスをあおり、白濁の酒を飲み干した。
何度かせき込みつつ、ようやく平静を取り戻した杉下は、闇に慣れた目で女の様子をうかがう。
目尻のあがった細い目の周囲は紫色のアイシャドーで彩られ、厚みのある唇には真紅のルージュが塗り込められている。身につけた黒いロングドレスはレース模様で、ところどころから白い素肌が透けて見える。
束ねて頭頂で盛りあげられた黒い髪。細身のスタイルながら、胸のふくらみは豊かだ。
「お代わりは、いい?」
「はい、もう結構です」
「じゃあ、行きましょうか」
女は体重をまったく感じさせない仕草で、脚の長い椅子からおりた。
「行くって、どこへ」
「あら、それが目的できたんでしょ、わたしのお店へ」
「それは、そう……」
「じゃあ、行きましょ」
女は手を差し伸べる。杉下は、その手にふれる。しなやかな指の感触が杉下の緊張をいっそうたかのぼらせ、手のひらの冷ややかな温度が胸の筋肉を激しく揺さぶった。
カウンターを離れてホールを横切り、カーテンで閉ざされた奥の部屋へと導かれる。その部屋には天井から無数の電気ランプがぶら下げられ、壁には一面にステンドグラスが埋め込まれていた。
部屋一面を支配する巨大なベッド。その上に女は腰をおろし、杉下を手招きする。杉下は、ベッドによじのぼって女の横に場所を取り、きらびやかな天井と壁を眺めた。
ランプの赤や青、緑、黄色の光が、それぞれ意思を持っているかのごとくきらめいている。そんな空間に包まれ、杉下は万華鏡の中に迷い込んだような錯覚をおぼえる。
原色の明かりが交錯して幻惑の音楽を奏でる。沈黙のつぶやきが、杉下の緊張をやわらかくほぐしていく。
ひざ立ちになった女は、スルスルとドレスを落とし、束ねていた髪をほどく。杉下は視線を女に向け、思わず息を呑んでしまった。
ドレスと同じ色をした下着に身を包んだ女は、白い素肌に原色の光を浴びながら、艶然とした表情を浮かべていた。
胸元から腰にいたるなだらかな曲線。豊満な乳房のふくらみと、くっきりとした胸の谷間に、杉下の目は吸い寄せられる。
女はまどろみの眼差しで杉下を見つめつつ、四つん這いになってにじり寄ってくる。
「夢の世界へようこそ」
女は杉下の耳もとでささやき、その唇をふさいだ。
さっき舐めた強い酒精のせいもあるのか、杉下の意識はもうろうとなる。筋肉は力を失い、神経が弛緩する。
女はあお向けに横たわった杉下の衣服を、ゆでタマゴの殻をむくようにはがしていった。
全裸になっても羞恥は感じない。目を閉じても、まぶたの裏に光がまたたく。
女はあばら骨の浮き出た杉下の胸板を舐め、乳首をくすぐり、みぞおちから下腹まで舌をすべらせる。そして、いまだ力のこもっていない一物を指でつまむと、舌先で鈴口をペロリとさぐった。
「ん、んん……」
ゆるんでいた神経が鋭敏になる。快感が脊髄から脳髄に突き抜ける。と同時に、全身の血液が股間に集中する。
女は、かすかに震えながら屹立する男根のカリ首をぬぐい、裏筋をなぞって陰嚢をふくんだ。
「ふふふ、おいしい。ねえ、気持ちいい? 気持ちいいでしょ」
「はい」
「びくんびくんってなってよろこんでる。あなたのオチンチン。ふふ、かわいい」
杉下をしごきつつ、女は左右の球を交互に舐る。そして、真っ赤な唇を大きく開くと、いきなり根元まで吞み込んだ。
「あ……!」
唾液のぬるみと口腔の温かさにおおいつくされる。女はゆっくりと頭を上下させ、首を揺らす。舌が縦横無尽に絡みつき、杉下の悦楽をあおってくる。
「ふうううん、はうん、はん……。先からいやらしいお汁がいっぱい出てくる。気持ちいいんだ。うれしい」
女は淫妖にほほ笑むと、杉下を見つめながら咥え、しゃぶりつきを激しくした。
ぢゅくちゅく、くちゅちゅぶと猥雑な音がひびく。まとわりつく内ほほの粘膜でこすられ、舌の刺激を受け止めながら杉下は頂点の迫りをおぼえる。
「ああ、もう……」
「出して、お口に出して。遠慮しないで」
首を左右に振りながら、女は上下の動きを止めない。我慢の限界を知った杉下は、そのまま濃厚な精液を、数度に分けて放ったのだった。
女はほおばったまま、吐き出された粘液を飲み込む。業物は力を失いつつあったが、女は口戯を続けて簡単に復活させた。
「うん……、ふふふ、元気ね。元気なオチンチン、大好き」
女はいったん杉下から身体を離し、ブラジャーの肩ひもをずらす。そして背中に手をまわしてホックをはずし、たわわに実った胸乳をあからさまにする。
谷間の切れ込みをそのままに、脇から輪郭がはみ出る乳塊。頂点に桜色の彩りをそえ、豊潤な丸みを誇示する。
「ごちそうしてあげる」
女は杉下におおいかぶさり、顔面に乳房を押し当てた。息苦しさを感じながらも、杉下は乳首をふくみ、舌で転がす。
「そう、おじょうず。お好きなように味わって」
杉下は両手で房を支え、指を食い込ませながらわしづかみにする。水風船のような柔軟さが極度の興奮をうながし、細胞の一つ一つがざわざわと色めき立つ。
「ねえ、もう挿れたい? 挿れたいの? わたしのオ×ンコに、あなたのオチンチン、挿れたい?」
「い、挿れたい」
「挿れてどうするの? 奥まですぼって挿れてどうするの?」
「気持ちよくなりたい」
「気持ちいいのかしら、わたしのオ×コ。ねえ、どう思う? わたしのオ×ンコの中、ぐぢゅぐぢゅに濡れたオ×ンコ、スケベなオツユでいっぱいになったオ×ンコに挿れたら気持ちいいのかしら。そんな中に挿れて、ズンズンかき混ぜたら、あなた、どうなっちゃうの?」
乳房をふくませ、杉下を握って弄びながら、女は淫靡な言葉を吐き続ける。
杉下の頭の中は、女の声に支配される。まだ挿入にはいたっていないにもかかわらず、すでにめり込ませているような感覚に浸る。
「ねえ、どうしたいの? 挿れてから、どうするの?」
「挿れたり、出したりしたい」
「挿れて、出して、ヒダヒダでオチンチンこすって……。気持ちよくなったら、最後はどうなるの?」
「出したい、出したいです」
「なにを?」
「ザーメン」
「どこに?」
「中に」
「中に出したら、赤ちゃんできちゃうわよ。うふふふ、でも、それでもいいかな。ねえ、どう思う」
女の質問に杉下は答えようがない。それでも、早く埋没させたい意志は強い。
「大丈夫、心配しないで。いじわるいってごめんなさい。おクスリ飲んでるから大丈夫。さあ、挿れるわよ。挿れて、いっぱい抜き差しして、最後はいっぱい、濃いの、熱いの吐き出してね」
女は身を起こし、最後の1枚を取る。そして、杉下にまたがると、自ら内部へと迎え入れた。
「やん……、すごい、固い……。うん、届いてる、一番奥まで届いてる」
膣襞がまとわりつき、肉筒が圧縮する。強い締めつけが肉棒の全体をおおい、愛蜜の潤いが包皮から芯へ染み込んでくる。
女は杉下の腹に手を置き、腰を前後左右に揺さぶる。膣内に納まった男根は、女の動きに合わせて攪拌する。
あふれ出た淫汁が互いの股間を濡らす。女の胸が揺れ、長い髪が乱れ舞う。
顎をあげ、背中を反らして女は躍った。ゆるく開いた唇から舌先が顔をのぞかせ、並びのいい歯がかいま見える。
「やあん、いい、気持ちいい。中が、中が気持ちいい。届いてるの、あなたので子宮の入り口が突かれてるの。うん、いい……。ねえ、気持ちいい? わたしの身体はあなたを気持ちよくしてあげてる?」
「いいです、すごく気持ちいいです」
「うれしい、ねえ、もっといって、もっとわたしをほめて」
「いいです、最高です、すごくいいです」
「やだ、言葉が足りない。でもいい……、やだ、すごい、頭の先から突き抜けちゃいそう」
ランプとガラスを通した明かりが、女の素肌を妖しく染める。女の姿は幽艶となって周囲に溶け込み、それでも確固とした存在感を示す。
杉下は女と一体化していることに、この上ない多幸感を得ていた。
このまま混じりあって、女の一部として溶け込んでもいい。そうすれば、永遠の喜悦が約束される。自分も、自分を取り巻く全部を意識しないでいい。あらゆるわずらわしさから解放される。
しかし、最後は間近まで迫っていた。杉下の精液だまりは、暴発の瞬間を迎えつつあった。
「ああ、ダメだ、もったいない」
「どうしたの? 出ちゃいそうなの」
「いやだ、まだ、感じていたい」
「わがままね……、うん、わたしもイッちゃう。ねえ、出して、中にいっぱいぶちまけて」
「いや……、ああ、でも」
「あああん、キテ、いっぱいキテ、やんやん、だめぇ、イク、やん……!」
女と同時に杉下は達した。精液だけでなく、体液のすべてを放出するような勢いで、ほとばしりは女の胎内に注ぎ込まれていった。
「どうだった。世界が変わっただろ」
数日後、林田は大学でベンチにいる杉下に話しかけた。
「ああ、変わった」
「それはよかった。けど、これからは自分の力で女を抱くんだ。マダムは二度と相手をしてくれない」
「本当か」
「ああ、本当だ。けれど、最後に人の役に立ててよかった。じゃあ、きみはこれからも人生を楽しみたまえ」
妙なことをいうものだ。そう思いながら、杉下は林田を見送る。林田は、蒼空をあおぎながら校舎の中に消えていった。
次の講義がはじまる時間になる。杉下はベンチから立ち上がり、教室に向かおうとする。
そのときだった。
「キャー!」
「飛び降りだ!」
校内が騒然となる。杉下は騒ぎの現場に駆けつける。そこにはうつぶせになって血を流す林田の姿があった。
その日、杉下は女の店に向かった。階段をおり、ドアを開け、暗い店内に入る。
女はいた。カウンターでほおづえをつき、タバコをくゆらせて椅子に座っている。
「あの、ペルノーを」
たたずんだまま、杉下はいう。
「この店はね、もうあなたのくるところじゃないの。悪いけど、帰って」
女は振り向きもしないでいう。
「けど……」
そのとき、バーテンダーが杉下をにらみつける。その眼光は、杉下に言葉のつむぎを許さない力に満ちていた。
しかたなく、杉下は店をあとにした。春が終わって夏が来れば、杉下は二十歳になる。
- 【長月猛夫プロフィール】
- 1988年官能小説誌への投稿でデビュー。1995年第1回ロリータ小説大賞(綜合図書主催)佳作。主な著作『ひとみ煌きの快感~美少女夢奇譚』(蒼竜社)/『病みたる性本能』(グリーンドア文庫)/『19歳に戻れない』(扶桑社・電子版)ほか。
この記事の画像
関連キーワード
 Linkage
関連記事
Linkage
関連記事
-

【昭和官能エレジー】第46回「文通セックスの結末」長月猛夫
-

【昭和官能エレジー】第45回「チンピラ男と拾われた女」長月…
-

【昭和官能エレジー】第44回「淫欲にいざなう椿の精」長月猛夫
-

【昭和官能エレジー】第43回「リリーという名の娼婦」長月猛夫
-

【昭和官能エレジー】第42回「見習いの犠牲になった二十歳の…
-

【昭和官能エレジー】第41回「ビデオからあらわれた不思議少…
-

【昭和官能エレジー】第40回「友人の姉の裏切り」長月猛夫
-

【昭和官能エレジー】第39回「見られてしまった教室での痴戯…
-

【いいおっぱいの日!特別コラム】「日本近代史におけるおっぱ…
-

【昭和官能エレジー】第38回「同棲相手との40年ぶりの再会…
-

あの週刊大衆が完全バックアップした全国の優良店を紹介するサイト